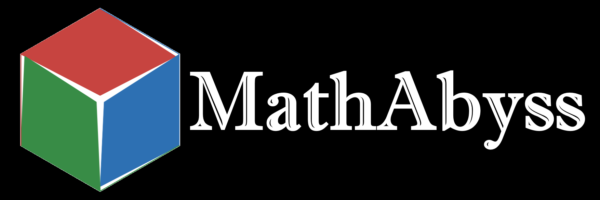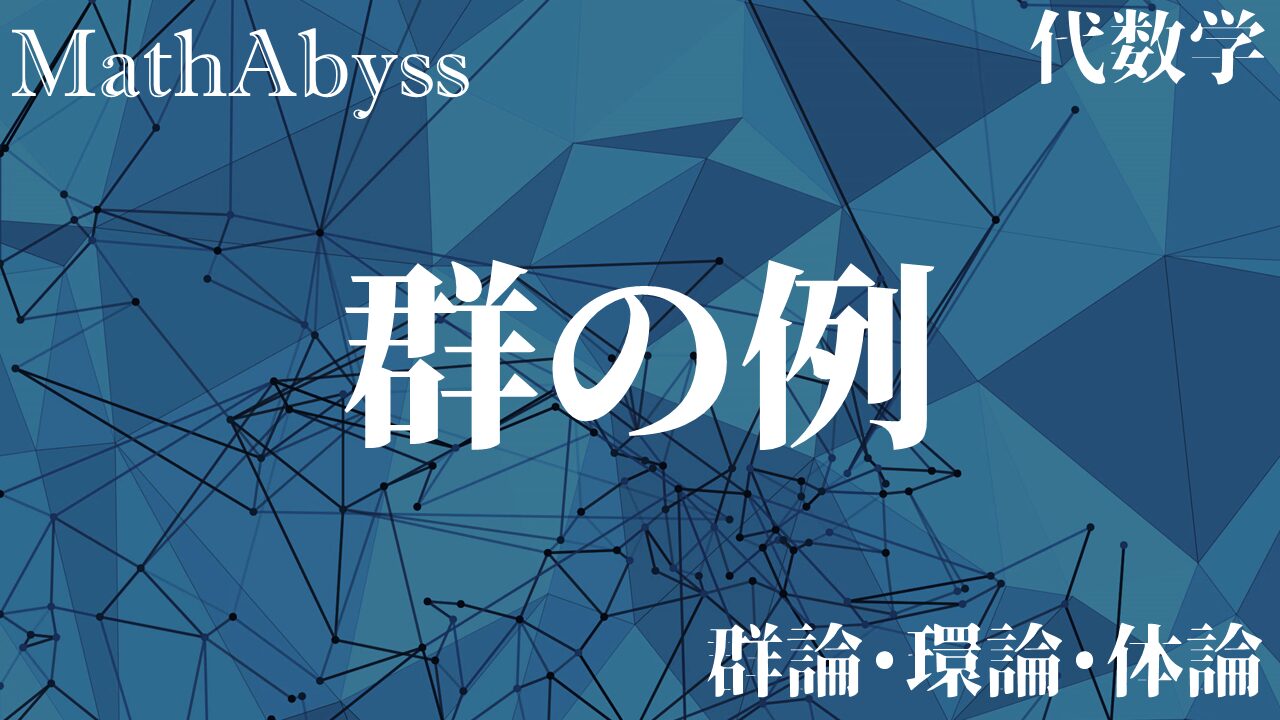群論では,様々な群の例が登場する.ここでは,重要度の高い群を列挙してまとめた.
加法・乗法の群
$\mathbb{Z},\mathbb{Q},\mathbb{R},\mathbb{C}$
$\mathbb{Z},\mathbb{Q},\mathbb{R},\mathbb{C}$は加法に関して可換群である.
$G\in \{ \mathbb{Z},\mathbb{Q},\mathbb{R},\mathbb{C}\}$とする.
- 任意の$a,b\in G$に対して
\[ a+b\in G\]
である. - 任意の$a,b,c\in G$に対して
\[ (a+b)+c=a+(b+c)\]
が成り立つ. - $0\in G$であり,任意の$a\in G$に対して
\[ a+0=0+a=a\]
が成り立つ. - 任意の$a\in G$に対して,$-a\in G$であり
\[ a+(-a)=(-a)+a=0\]
が成り立つ.
いずれも無限群である.
特に,$\mathbb{Z}=\langle 1\rangle$は加法に関して$1$を生成元とする巡回群である.
$\mathbb{Z}$の部分群
$n\in \mathbb{N}\cup \{ 0\}$,$n\mathbb{Z}$を$n$の倍数全体の集合とする.
$n\mathbb{Z}$は$\mathbb{Z}$の加法に関する部分群である.
$a,b\in n\mathbb{Z}$を任意にとる.
このとき,$b$の逆元は$-b$であり,$a-b$は$n$の倍数であるから
\[ a-b\in n\mathbb{Z}\]
したがって,$n\mathbb{Z}$は$\mathbb{Z}$の部分群である1.
特に,$n\mathbb{Z}$は$n\neq 0$のとき無限群であり,加法に関して$n$を生成元とする巡回群である.
$\mathbb{Z}$の部分群は$n\mathbb{Z}$のみである.
$\mathbb{Q}\setminus \{ 0\} ,\mathbb{R}\setminus \{ 0\} ,\mathbb{C}\setminus \{ 0\}$
$\mathbb{Q}^{\times}=\mathbb{Q}\setminus \{ 0\} ,\mathbb{R}^{\times}=\mathbb{R}\setminus \{ 0\} ,\mathbb{C}^{\times}=\mathbb{C}\setminus \{ 0\}$は乗法に関して可換群である.
$G\in \{ \mathbb{Q}^{\times},\mathbb{R}^{\times},\mathbb{C}^{\times}\}$とする.
- 任意の$a,b\in G$に対して
\[ ab\in G\]
である. - 任意の$a,b,c\in G$に対して
\[ (ab)c=a(bc)\]
が成り立つ. - $1\in G$であり,任意の$a\in \{ \pm 1\}$に対して
\[ a1=1a=a\]
が成り立つ. - 任意の$a\in G$に対して,$a^{-1}\in G$であり
\[ aa^{-1}=a^{-1}a=1\]
が成り立つ.
いずれも無限群である.
位数$の群
$\{ \pm 1\}$は乗法に関して位数$2$の可換群である.
$\{ \pm 1\}$の乗法表は次のようになる.
| $\times$ | $1$ | $-1$ |
| $1$ | $1$ | $-1$ |
| $-1$ | $-1$ | $1$ |
- 任意の$a,b\in \{ \pm 1\}$に対して
\[ ab\in \{ \pm 1\} \]である. - 任意の$a,b,c\in \{ \pm 1\}$に対して
\[ (ab)c=a(bc)\]が成り立つ. - $1\in \{ \pm 1\}$であり,任意の$a\in \{ \pm 1\}$に対して
\[ a1=1a=a\]
が成り立つ. - 任意の$a\in \{ \pm 1\}$に対して,$a^{-1}\in \{ \pm 1\}$であり
\[ aa^{-1}=a^{-1}a=1\]
が成り立つ.
位数$2$の任意の群は,この群$\{ \pm 1\}$と同型である.したがって,位数$2$の群は本質的には1種類しか存在しない.
置換群
$n$次対称群$\mathfrak{S}_n$
$n\in \mathbb{N}$,$\mathfrak{S}_n$を全単射
\[ \sigma :\{ 1,2,\dots ,n\} \to \{ 1,2,\dots ,n\} \]
全体の集合とする.
$\mathfrak{S}_n$は写像の合成に関して群である.
- 任意の$\sigma ,\tau \in \mathfrak{S}_n$に対して
\[ \sigma \circ \tau \in \mathfrak{S}_n\]
である. - 任意の$\sigma ,\tau ,\upsilon \in \mathfrak{S}_n$に対して
\[ (\sigma \circ \tau )\circ \upsilon =\sigma \circ (\tau \circ \upsilon )\]
が成り立つ. - 恒等写像$\mathrm{id}\in \mathfrak{S}_n$が存在して,任意の$\sigma \in \mathfrak{S}_n$に対して
\[ \sigma \circ \mathrm{id}=\mathrm{id}\circ \sigma =\sigma \]
が成り立つ. - 任意の$\sigma \in \mathfrak{S}_n$に対して,逆写像$\sigma ^{-1}\in \mathfrak{S}_n$が存在して
\[ \sigma \sigma ^{-1}=\sigma ^{-1}\sigma =\mathrm{id}\]
が成り立つ.
このとき,$\mathfrak{S}_n$を$n$次対称群($n$-th symmetric group)といい,位数$n!$の有限群である.
$n$次交代群$\mathfrak{A}_n$
$n\in \mathbb{N}$とする.
集合
\[ \mathfrak{A}_n=\{ \sigma \in \mathfrak{S}_n\mid \operatorname{sgn}\sigma =1\} \]
は$n$次対称群$\mathfrak{S}_n$の正規部分群である.
置換の符号を与える$\mathfrak{S}_n$から位数$2$の群$\{ \pm 1\}$への写像
\[ \operatorname{sgn}:\mathfrak{S}_n\to \{ \pm 1\} \]
を考える.
任意の$\sigma ,\tau \in \mathfrak{S}_n$に対して
\[ \operatorname{sgn}(\sigma \circ \tau)=(\operatorname{sgn}\sigma )(\operatorname{sgn}\tau )\]
が成り立つ2から,$\operatorname{sgn}$は準同型写像である.
よって,$\mathfrak{A}_n=\operatorname{Ker}\operatorname{sgn}\triangleleft \mathfrak{S}_n$である3.
このとき,$\mathfrak{A}_n$を$n$次交代群($n$-th alternating group)といい,$n=1$のときは位数$1$,$n\neq 1$のときは位数$\dfrac{n!}{2}$の有限群である.
行列の積の群
一般線形群$\mathrm{GL}_n(K)$
$n\in \mathbb{N}$,$K$を体4,$\mathrm{GL}_n(K)$を$K$上の$n$次正則行列全体の集合とする.
$\mathrm{GL}_n(K)$は行列の積に関して群である.
- 任意の$A,B\in \mathrm{GL}_n(K)$に対して
\[ AB\in \mathrm{GL}_n(K)\]
である. - 任意の$A,B,C\in \mathrm{GL}_n(K)$に対して
\[ (AB)C=A(BC)\]
が成り立つ. - 単位行列$I_n\in \mathrm{GL}_n(K)$が存在して,任意の$A\in \mathrm{GL}_n(K)$に対して
\[ AI_n=I_nA=A\]
が成り立つ. - 任意の$A\in \mathrm{GL}_n(K)$に対して,逆行列$A^{-1}\in \mathrm{GL}_n(K)$が存在して
\[ AA^{-1}=A^{-1}A=I_n\]
が成り立つ.
このとき,$\mathrm{GL}_n(K)$を一般線形群(general linear group)という5.
特殊線形群$\mathrm{SL}_n(K)$
$n\in \mathbb{N}$,$K$を体とする.
集合
\[ \mathrm{SL}_n(K)=\{ A\in \mathrm{GL}_n(K)\mid \det A=1\} \]
は一般線形群$\mathrm{GL}_n(K)$の行列の積に関する正規部分群である.
$A,B\in \mathrm{SL}_n(K)$を任意にとる.
このとき,$B$の逆元は逆行列$B^{-1}$である6.
\[ (AB^{-1})(BA^{-1})=(BA^{-1})(AB^{-1})=I_n\]
であるから,$AB^{-1}$は正則であり
\[ \det (AB^{-1})=(\det A)(\det B^{-1})=\frac{\det A}{\det B}=1\]
であるから
\[ AB^{-1}\in \mathrm{SL}_n(K)\]
また,任意の$A\in \mathrm{SL}_n(K)$と任意の$B\in \mathrm{GL}_n(K)$に対して
\[ \det (BAB^{-1})=\frac{(\det B)(\det A)}{\det B}=\det A=1\]
が成り立つから
\[ BAB^{-1}\in \mathrm{SL}_n(K)\]
したがって,$\mathrm{SL}_n(K)\triangleleft \mathrm{GL}_n(K)$である.
このとき,$\mathrm{SL}_n(K)$を特殊線形群(special linear group)という7.
直交群$\mathrm{O}_n(K)$
$n\in \mathbb{N}$,$K$を体とする.
集合
\[ \mathrm{O}_n(K)=\{ A\in \mathrm{GL}_n(K)\mid {}^tAA=I_n\} \]
は一般線形群$\mathrm{GL}_n(K)$の行列の積に関する部分群である.
$A,B\in \mathrm{O}_n(K)$を任意にとる.
このとき,$B$の逆元は$B^{-1}={}^tB$である8.
\[ {}^t(A{}^tB)(A{}^tB)=B{}^tAA{}^tB=B{}^tB=I_n\]
であるから
\[ A{}^tB\in \mathrm{O}_n(K)\]
したがって,$\mathrm{O}_n(K)$は$\mathrm{GL}_n(K)$の部分群である.
このとき,$\mathrm{O}_n(K)$を直交群(orthogonal group)という9.
特殊直交群$\mathrm{SO}_n(K)$
$n\in \mathbb{N}$,$K$を体とする.
集合
\[ \mathrm{SO}_n(K)=\mathrm{O}_n(K)\cap \mathrm{SL}_n(K)\]
は$\mathrm{O}_n(K)$の行列の積に関する部分群である.
$A,B\in \mathrm{SO}_n(K)$を任意にとる.
このとき,$B$の逆元は$B^{-1}={}^tB$である.
\[ {}^t(A{}^tB)(A{}^tB)=B{}^tAA{}^tB=B{}^tB=I_n\]
であり
\[ \det (AB^{-1})=(\det A)(\det B^{-1})=\frac{\det A}{\det B}=1\]
であるから
\[ A{}^tB\in \mathrm{SO}_n(K)\]
したがって,$\mathrm{SO}_n(K)$は$\mathrm{O}_n(K)$の部分群である.
このとき,$\mathrm{SO}_n(K)$を特殊直交群(special orthogonal group)(または回転群(rotation group))という10.
特に
\[ \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})=\left\{ \begin{pmatrix}\cos \theta &-\sin \theta \\ \sin \theta &\cos \theta \end{pmatrix}\ \middle| \ \theta \in \mathbb{R}\right\} \]
である.
斜交群$\mathrm{Sp}_{2n}(K)$
$n\in \mathbb{N}$,$K$を体とする.また,$2n$次正方行列$J_n$を
\[ J_n=\begin{pmatrix}O&I_n\\ -I_n&O\end{pmatrix}\]
とする.
集合
\[ \mathrm{Sp}_{2n}(K)=\{ A\in \mathrm{GL}_{2n}(K)\mid {}^tAJ_nA=J_n\} \]
は一般線形群$\mathrm{GL}_{2n}(K)$の行列の積に関する部分群である.
$A,B\in \mathrm{Sp}_{2n}(K)$を任意にとる.
このとき,$B$の逆元は逆行列$B^{-1}$である.
\[ {}^tBJ_nB=J_n\]
の両辺に左から${}^tB^{-1}$を,右から$B^{-1}$を掛けると
\[ J_n={}^tB^{-1}J_nB^{-1}\]
となり,このとき
\[ {}^t(AB^{-1})J_n(AB^{-1})={}^tB^{-1}{}^tAJ_nAB^{-1}={}^tB^{-1}J_nB^{-1}=J_n\]
であるから
\[ AB^{-1}\in \mathrm{Sp}_{2n}(K)\]
したがって,$\mathrm{Sp}_{2n}(K)$は$\mathrm{GL}_n(K)$の部分群である.
このとき,$\mathrm{Sp}_{2n}(K)$を斜交群(またはシンプレクティック群)(symplectic group)という11.
ユニタリ群$\mathrm{U}(n)$
$n\in \mathbb{N}$とする.
集合
\[ \mathrm{U}(n)=\{ A\in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})\mid {}^t\overline{A}A=I_n\} \]
は一般線形群$\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$の行列の積に関する部分群である.
$A,B\in \mathrm{U}(n)$を任意にとる.
このとき,$B$の逆元は逆行列$B^{-1}$である.
\[ {}^t\overline{B}B=I_n\]
の両辺に左から${}^t\overline{B}^{-1}$を,右から$B^{-1}$を掛けると
\[ I_n={}^t\overline{B}^{-1}B^{-1}\]
となり,このとき
\[ {}^t\overline{AB^{-1}}(AB^{-1})={}^t\overline{B}^{-1}{}^t\overline{A}AB^{-1}={}^t\overline{B}^{-1}B^{-1}=I_n\]
であるから
\[ AB^{-1}\in \mathrm{U}(n)\]
したがって,$\mathrm{U}(n)$は$\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$の部分群,特に無限群である.
このとき,$\mathrm{U}(n)$をユニタリ群(unitary group)という12.
特殊ユニタリ群$\mathrm{SU}(n)$
$n\in \mathbb{N}$とする.
集合
\[ \mathrm{SU}(n)=\mathrm{U}(n)\cap \mathrm{SL}_n(\mathbb{C})\]
はユニタリ群$\mathrm{U}(n)$の行列の積に関する部分群である.
$A,B\in \mathrm{SU}(n)$を任意にとる.
このとき,$B$の逆元は逆行列$B^{-1}$である.
\[ {}^t\overline{B}B=I_n\]
の両辺に左から${}^t\overline{B}^{-1}$を,右から$B^{-1}$を掛けると
\[ I_n={}^t\overline{B}^{-1}B^{-1}\]
となり,このとき
\[ {}^t\overline{AB^{-1}}(AB^{-1})={}^t\overline{B}^{-1}{}^t\overline{A}AB^{-1}={}^t\overline{B}^{-1}B^{-1}=I_n\]
である.また
\[ \det (AB^{-1})=(\det A)(\det B^{-1})=\frac{\det A}{\det B}=1\]
であるから
\[ AB^{-1}\in \mathrm{SU}(n)\]
したがって,$\mathrm{SU}(n)$は$\mathrm{U}(n)$の部分群,特に無限群である.
このとき,$\mathrm{SU}(n)$を特殊ユニタリ群(special unitary group)という.
四元数群$Q_8$
\[ 1^{\prime}=\begin{pmatrix}1&0\\ 0&1\end{pmatrix}\in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})\\ i^{\prime}=\begin{pmatrix}i&0\\ 0&-i\end{pmatrix}\in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})\\ j^{\prime}=\begin{pmatrix}0&1\\ -1&0\end{pmatrix}\in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})\\ k^{\prime}=\begin{pmatrix}0&i\\ i&0\end{pmatrix}\in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})\]
とする.
集合
\[ Q_8=\{ \pm 1^{\prime},\pm i^{\prime},\pm j^{\prime},\pm k^{\prime}\} \]
は一般線形群$\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$の行列の積に関する部分群である.
$Q_8$の乗法表は次のようになる.
| $\times$ | $1^{\prime}$ | $-1^{\prime}$ | $i^{\prime}$ | $-i^{\prime}$ | $j^{\prime}$ | $-j^{\prime}$ | $k^{\prime}$ | $-k^{\prime}$ |
| $1^{\prime}$ | $1^{\prime}$ | $-1^{\prime}$ | $i^{\prime}$ | $-i^{\prime}$ | $j^{\prime}$ | $-j^{\prime}$ | $k^{\prime}$ | $-k^{\prime}$ |
| $-1^{\prime}$ | $-1^{\prime}$ | $1^{\prime}$ | $-i^{\prime}$ | $i^{\prime}$ | $-j^{\prime}$ | $j^{\prime}$ | $-k^{\prime}$ | $k^{\prime}$ |
| $i^{\prime}$ | $i^{\prime}$ | $-i^{\prime}$ | $-1^{\prime}$ | $1^{\prime}$ | $k^{\prime}$ | $-k^{\prime}$ | $-j^{\prime}$ | $j^{\prime}$ |
| $-i^{\prime}$ | $-i^{\prime}$ | $i^{\prime}$ | $1^{\prime}$ | $-1^{\prime}$ | $-k^{\prime}$ | $k^{\prime}$ | $j^{\prime}$ | $-j^{\prime}$ |
| $j^{\prime}$ | $j^{\prime}$ | $-j^{\prime}$ | $-k^{\prime}$ | $k^{\prime}$ | $-1^{\prime}$ | $1^{\prime}$ | $i^{\prime}$ | $-i^{\prime}$ |
| $-j^{\prime}$ | $-j^{\prime}$ | $j^{\prime}$ | $k^{\prime}$ | $-k^{\prime}$ | $1^{\prime}$ | $-1^{\prime}$ | $-i^{\prime}$ | $i^{\prime}$ |
| $k^{\prime}$ | $k^{\prime}$ | $-k^{\prime}$ | $j^{\prime}$ | $-j^{\prime}$ | $-i^{\prime}$ | $i^{\prime}$ | $-1^{\prime}$ | $1^{\prime}$ |
| $-k^{\prime}$ | $-k^{\prime}$ | $k^{\prime}$ | $-j^{\prime}$ | $j^{\prime}$ | $i^{\prime}$ | $-i^{\prime}$ | $1^{\prime}$ | $-1^{\prime}$ |
$Q_8$は行列の積に関して閉じており,行列の積は結合律を満たし,単位元は$1^{\prime}\in Q_8$である.
また,$Q_8$の元それぞれの逆元は
\[ (\pm 1^{\prime})^{-1}=\pm 1^{\prime}\\ (\pm i^{\prime})^{-1}=\mp i\\ (\pm j^{\prime})^{-1}=\mp j\\ (\pm k^{\prime})^{-1}=\mp k\]
であるから(複号同順),$Q_8$は$\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$の部分群である.
このとき,$Q_8$を四元数群(quaternion group)といい,位数$8$の有限群である.
モジュラー群$\Gamma$
$\Gamma$を行列式が$1$である整数成分の$2$次正方行列全体の集合とする.
$\Gamma$は一般線形群$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$の行列の積に関する部分群である.
\[ A=\begin{pmatrix}a&b\\ c&d\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}e&f\\ g&h\end{pmatrix}\in \Gamma \]
を任意にとる.
このとき,$B$の逆元は逆行列$B^{-1}$であり
\[ AB^{-1}=\begin{pmatrix}a&b\\ c&d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}h&-f\\ -g&e\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}ah-bg&-af+be\\ ch-dg&-cf+de\end{pmatrix}\]
である.また
\[ \det (AB^{-1})=(\det A)(\det B^{-1})=\frac{\det A}{\det B}=1\]
であるから
\[ AB^{-1}\in \Gamma \]
したがって,$\Gamma$は$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$の部分群,特に無限群である.
このとき,$\Gamma$をモジュラー群(modular group)という.
対称移動・回転移動の群
二面体群$D_n$
$n\in \mathbb{N}$とする.
群
\[ D_n=\left\langle \begin{pmatrix}\cos \frac{2\pi}{n}&-\sin \frac{2\pi}{n}\\ \sin \frac{2\pi}{n}&\cos \frac{2\pi}{n}\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0\\ 0&-1\end{pmatrix}\right\rangle \]
を二面体群(dihedral group)といい,位数$2n$の有限群である13.
\[ \begin{pmatrix}\cos \frac{2\pi}{n}&-\sin \frac{2\pi}{n}\\ \sin \frac{2\pi}{n}&\cos \frac{2\pi}{n}\end{pmatrix}\]
は反時計回りの$\dfrac{2\pi}{n}$の回転移動を表し
\[ \begin{pmatrix}1&0\\ 0&-1\end{pmatrix}\]
は$x$軸に関する対称移動を表す.
クラインの四元群$V_4$
\[ V_4=\left\{ \begin{pmatrix}1&0\\ 0&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1&0\\ 0&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0\\ 0&-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1&0\\ 0&-1\end{pmatrix}\right\} \]
は群である.
\[ I=\begin{pmatrix}1&0\\ 0&1\end{pmatrix}\\ T=\begin{pmatrix}-1&0\\ 0&1\end{pmatrix}\\ T^{\prime}=\begin{pmatrix}1&0\\ 0&-1\end{pmatrix}\\ TT^{\prime}=\begin{pmatrix}-1&0\\ 0&-1\end{pmatrix}\]
とおくと,$V_4$の乗法表は次のようになる.
| $\times$ | $I$ | $T$ | $T^{\prime}$ | $TT^{\prime}$ |
| $I$ | $I$ | $T$ | $T^{\prime}$ | $TT^{\prime}$ |
| $T$ | $T$ | $I$ | $TT^{\prime}$ | $T^{\prime}$ |
| $T^{\prime}$ | $T^{\prime}$ | $TT^{\prime}$ | $I$ | $T$ |
| $TT^{\prime}$ | $TT^{\prime}$ | $T^{\prime}$ | $T$ | $I$ |
$V_4$は行列の積に関して閉じており,行列の積は結合律を満たし,単位元は$I\in V_4$である.
また,$V_4$の元それぞれの逆元は
\[ I^{-1}=I\\ T^{-1}=T\\ (T^{\prime})^{-1}=T^{\prime}\\ (TT^{\prime})^{-1}=TT^{\prime}\]
であるから,$V_4$は可換群である.
このとき,$V_4$をクラインの四元群(Klein four-group)といい,位数$4$の有限群である.
$I$は恒等変換,$T$は$y$軸に関する対称移動,$T^{\prime}$は$x$軸に関する対称移動,$TT^{\prime}$は原点に関する対称移動を表す.
正多面体群
正多面体をそれ自身に重ねる3次元空間の回転全体の集合は群になる.この群を正多面体群(polyhedral group)という.
正四面体群(tetrahedral group)は$4$次交代群$\mathfrak{A}_4$,正六面体群(hexahedral group)及び正八面体群(octahedral group)は$4$次対称群$\mathfrak{S}_4$,正十二面体群(dodecahedral group)及び正二十面体群(icosahedral group)は$5$次交代群$\mathfrak{A}_5$と同型である.
正多面体群の元は,回転軸が頂点を通る回転移動,回転軸が辺の中点を通る回転移動,回転軸が面の重心を通る回転移動を表す.
- 部分群であるための必要十分条件は,次の記事の定理1を参照するとよい.
https://mathabyss.com/subgroup/ ↩︎ - 置換の符号の性質については次の記事の命題4の①を参照するとよい.
https://mathabyss.com/symmetric_group/#toc8 ↩︎ - 準同型写像の核が定義域の正規部分群であることは,次の記事を参照するとよい.
https://mathabyss.com/wait ↩︎ - 体の定義については次の記事を参照するとよい.
https://mathabyss.com/field/ ↩︎ - 群論では$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$や$\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$がよく登場する. ↩︎
- $B$は正則行列であるから,逆行列$B^{-1}$が存在する. ↩︎
- 群論では$\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$や$\mathrm{SL}_n(\mathbb{C})$がよく登場する. ↩︎
- $O_n(K)$の定義より,$B$の逆行列と転置行列は等しい. ↩︎
- 群論では$\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$や$\mathrm{O}_n(\mathbb{C})$がよく登場する.これらは$\mathrm{O}(n)$と略記される場合がある. ↩︎
- 群論では$\mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$や$\mathrm{SO}_n(\mathbb{C})$がよく登場する.これらは$\mathrm{SO}(n)$と略記される場合がある. ↩︎
- 群論では$\mathrm{Sp}_{2n}(\mathbb{R})$や$\mathrm{Sp}_{2n}(\mathbb{C})$がよく登場する.斜交群と呼ばれる群はもう一つあり,注意が必要である. ↩︎
- ユニタリ群は一般の体についても定義される. ↩︎
- 群の生成については次の記事を参照するとよい.
https://mathabyss.com/generating_set_of_a_group/ ↩︎