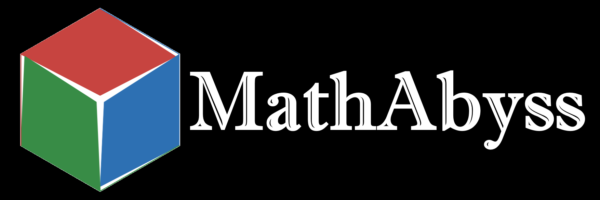線形代数学では行列と呼ばれる数学的対象を取り扱う.行列を考えることで,$n$次元ユークリッド空間の線形変換を機械的な計算で扱うことができるようになる.
行列の導入
高校数学では,ベクトルの成分表示を扱った.これは,$2$次元平面上のベクトルを2つの実数の組で,$3$次元空間上のベクトルを3つの実数の組で表すものであった.
線形代数学では,$n$次元空間上のベクトルを扱う.$n$次元空間上のベクトルは,同様に,$n$個の次数の組で表すことができる.
\[ (a_1,a_2,\dots ,a_n)\]
このようなベクトルを多数考えるとき,1つ1つのベクトルを考えるのではなく,まとめて考えることができるならば,より簡単に扱うことができそうである.
そこで,$m$次元空間上の$n$本のベクトルの組を次のように表すことにしよう.
\[ \begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots &a_{1n}\\ a_{21}&a_{22}&\cdots &a_{2n}\\ \vdots &\vdots &\ddots &\vdots \\ a_{m1}&a_{m2}&\cdots &a_{mn}\end{pmatrix}\]
これは,$n$本のベクトル
\[ (a_{11},a_{21},\dots a_{m1})\\ (a_{12},a_{22},\dots ,a_{m2})\\ \vdots \\ (a_{1n},a_{2n},\dots ,a_{mn})\]
をまとめて表現したものであり,行列と呼ばれている.
行列の定義
形式的には,行列は数などを長方形状に並べたものとして定義される.
$m,n\in \mathbb{N}$,$i\in \{ 1,2,\dots ,m\} ,j\in \{ 1,2,\dots ,n\}$,$a_{11},a_{12},\dots ,a_{mn}$を数学的対象1とする.
$a_{11},a_{12},\dots ,a_{mn}$を
\[ A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots &a_{1n}\\ a_{21}&a_{22}&\cdots &a_{2n}\\ \vdots &\vdots &\ddots &\vdots \\ a_{m1}&a_{m2}&\cdots &a_{mn}\end{pmatrix}\]
のように長方形状に並べたものを$m\times n$行列(または$m$行$n$列の行列,$(m,n)$型の行列)($m\times n$ matrix)といい,$(a_{ij})_{m\times n}$とも表す.また,$(m,n)$を行列$A$の型(またはサイズ)(size)という.
さらに,$a_{ij}$を行列$A$の$(i,j)$成分($(i,j)$ entry, (または$(i,j)$ component)),$i$や$j$を$a_{ij}$の添字(index)といい
\[ \begin{pmatrix}a_{i1}&a_{i2}&\cdots &a_{in}\end{pmatrix}\]
を行列$A$の第$i$行($i$-th row),
\[ \begin{pmatrix}a_{1j}\\ a_{2j}\\ \vdots \\ a_{mj}\end{pmatrix}\]
を行列$A$の第$j$列($j$-th column)という.
$1\times 1$行列$\begin{pmatrix}a\end{pmatrix}$は$a$と同一視する.
具体例を通して確認しよう.
\[ A=\begin{pmatrix}2&3&5\\ 7&11&13\end{pmatrix}\quad B=\begin{pmatrix}-3\\ 1\\ -4\end{pmatrix}\]
は行列である.特に,$A$は$3\times 2$行列,$B$は$1\times 3$行列である.
$2\times 3$行列
\[ \begin{pmatrix}1&2\\ 3&4\\ 5&6\end{pmatrix}\]
の第$3$行は
\[ \begin{pmatrix}5&6\end{pmatrix}\]
であり,第$2$列は
\[ \begin{pmatrix}2\\ 4\\ 6\end{pmatrix}\]
である.また,$(3,2)$成分は$6$である.
2つの行列が与えられたとき,その相等関係を次のように定義する.
$m,n\in \mathbb{N}$,$A=(a_{ij})_{m\times n}$を$m\times n$行列,$B=(b_{ij})_{p\times q}$を$p\times q$行列とする.
$m=p$かつ$n=q$であり,任意の$i\in \{ 1,2,\dots ,m\} ,j\in \{ 1,2,\dots ,n\}$に対して,$a_{ij}=b_{ij}$が成り立つとき,$A$と$B$は等しい(equal)といい,$A=B$で表す.
定義1で与えられた行列の定義は,厳密なものではない.より厳密には,写像を用いて次のように定義される.
$m,n\in \mathbb{N}$,$S$を集合とする.
写像
\[ A:\{ 1,2,\dots ,m\} \times \{ 1,2,\dots ,n\} \to S\]
を$m\times n$行列という.また
\[ a_{ij}\coloneqq A(i,j)\quad (i\in \{ 1,2,\dots ,m\} ,j\in \{ 1,2,\dots ,n\} )\]
とするとき,$A$を
\[ \begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots &a_{1n}\\ a_{21}&a_{22}&\cdots &a_{2n}\\ \vdots &\vdots &\ddots &\vdots \\ a_{m1}&a_{m2}&\cdots &a_{mn}\end{pmatrix}\]
で表す.
種々の行列
特に重要な性質を持つ行列には,名前がついている.
数ベクトル
$n\in \mathbb{N}$とする.
- $1\times n$行列を$n$次行ベクトル($n$-th row vector)という.
- $n\times 1$行列を$n$次列ベクトル($n$-th column vector)という.
- 行ベクトルと列ベクトルを合わせて数ベクトル(numerical vector)という.
- 任意の成分が$0$である数ベクトルを零ベクトル(zero vector)といい,$\bm{0}$で表す.
\[ \begin{pmatrix}3&1&4&1&5\end{pmatrix}\]
は$5$次行ベクトルである.
\[ \begin{pmatrix}2\\ 1\\ 3\end{pmatrix}\]
は$3$次列ベクトルである.
行列と成分
$K$を体とする.
- 任意の成分が$K$の元である行列を$K$上の行列(matrix over $K$)という.
- $\mathbb{R}$上の行列を実行列(real matrix)という.
- $\mathbb{C}$上の行列を複素行列(complex matrix)という.
$m,n\in \mathbb{N}$とする.
任意の成分が$0$である行列を零行列(zero matrix)といい,$O$で表す.
特に,$m\times n$行列である零行列を$O_{m,n}$で表す.
\[ O_{2,3}=\begin{pmatrix}0&0&0\\ 0&0&0\end{pmatrix}\]
正方行列
$n\in \mathbb{N}$,$i,j\in \{ 1,2,\dots ,n\}$,$A=(a_{ij})_{n\times n}$を$n\times n$行列とする.
- $A$を$n$次正方行列($n$-th square matrix)(または$n$次行列($n$-th matrix)といい,$a_{ii}$を$A$の対角成分(diagonal entry)という.
- $i\neq j$ならば$a_{ij}=0$であるとき,$A$を対角行列(diagonal matrix)という.
- $a_{11}=a_{22}=\dots =a_{nn}$かつ$A$が対角行列であるとき,$A$をスカラー行列(scalar matrix)という.
- $a_{11}=a_{22}=\dots =a_{nn}=1$かつ$A$が対角行列であるとき,$A$を単位行列(identity matrix)といい,$E$(または$I$),特に$E_n$(または$I_n$)で表す.
\[ E_4=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\ 0&1&0&0\\ 0&0&1&0\\ 0&0&0&1\end{pmatrix}\]
\[ \begin{pmatrix}3&0&0\\ 0&1&0\\ 0&0&4\end{pmatrix}\]
は$3$次正方行列,特に対角行列である.
$n\in \mathbb{N}$,$i,j\in \{ 1,2,\dots ,n\}$,$A=(a_{ij})_{n\times n}$を$n$次正方行列とする.
- $i>j$ならば$a_{ij}=0$であるとき,$A$を上三角行列(upper triangular matrix, right triangular matrix)という,
- $i<j$ならば$a_{ij}=0$であるとき,$A$を下三角行列(lower triangular matrix, left triangular matrix)という.
\[ \begin{pmatrix}1&2&3\\ 0&4&5\\ 0&0&6\end{pmatrix}\]
は上三角行列である.
\[ \begin{pmatrix}1&0&0\\ 2&4&0\\ 3&5&6\end{pmatrix}\]
は下三角行列である.
転置行列
$m,n\in \mathbb{N}$,$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots &a_{1n}\\ a_{21}&a_{22}&\cdots &a_{2n}\\ \vdots &\vdots &\ddots &\vdots \\ a_{m1}&a_{m2}&\cdots &a_{mn}\end{pmatrix}$を$m\times n$行列とする.
$n\times m$行列
\[ \begin{pmatrix}a_{11}&a_{21}&\cdots &a_{m1}\\ a_{12}&a_{22}&\cdots &a_{m2}\\ \vdots &\vdots &\ddots &\vdots \\ a_{1n}&a_{2n}&\cdots &a_{mn}\end{pmatrix}\]
を$A$の転置行列(transpose, transpose of a matrix, transposed matrix)といい,${}^tA$で表す.
また,${}^tA$を求めることを,$A$の転置をとる(transpose)という.
$A$を正方行列とする.
${}^tA=A$であるとき,$A$を対称行列(symmetric matrix)という.
\[ A=\begin{pmatrix}1&2&3\\ 4&5&6\end{pmatrix}\]
の転置行列は
\[ {}^tA=\begin{pmatrix}1&4\\ 2&5\\ 3&6\end{pmatrix}\]
\[ B=\begin{pmatrix}-1&1&2\\ 1&-2&3\\ 2&3&-3\end{pmatrix}\]
の転置行列は
\[ {}^tB=\begin{pmatrix}-1&1&2\\ 1&-2&3\\ 2&3&-3\end{pmatrix}\]
よって,${}^tB=B$であるから,$B$は対称行列である.
$n\in \mathbb{N}$,$A=(a_{ij})_{n\times n}$を$n$次正方行列とする.
$A$が対称行列であることの必要十分条件は,任意の$i,j\in \{ 1,2,\dots ,n\}$に対して,$a_{ij}=a_{ji}$が成り立つことである.
$A$は対称行列であるから
\[ {}^tA=A\]
すなわち
\[ \begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots &a_{1n}\\ a_{21}&a_{22}&\cdots &a_{2n}\\ \vdots &\vdots &\ddots &\vdots \\ a_{n1}&a_{n2}&\cdots &a_{nn}\end{pmatrix}= \begin{pmatrix}a_{11}&a_{21}&\cdots &a_{n1}\\ a_{12}&a_{22}&\cdots &a_{n2}\\ \vdots &\vdots &\ddots &\vdots \\ a_{1n}&a_{2n}&\cdots &a_{nn}\end{pmatrix}\]
このとき,任意の$i,j\in \{ 1,2,\dots ,n\}$に対して,$a_{ij}=a_{ji}$が成り立つ.$\blacksquare$
- 多くの場合は実数や複素数などの「数」である. ↩︎