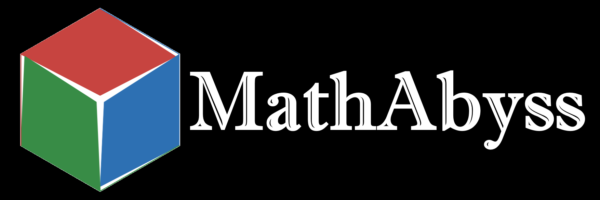複数のベクトル空間が与えられたとき,それらの関係性を記述することは非常に重要である.この記事では,そのために必要な線形写像の概念についてまとめた.
線形写像
線形写像を定義するにあたって,写像に関する知識が必要となる.詳しくは,次の記事を参照するとよい.
線形写像は,2つのベクトル空間の間を,その構造を保ったまま写す写像である.
$K$を体,$V,W$を$K$上のベクトル空間,$f:V\to W$を写像とする.
$f$が次の2つの条件
- 任意の$\bm{x},\bm{y}\in V$に対して
\[ f(\bm{x}+\bm{y})=f(\bm{x})+f(\bm{y})\]
が成り立つ. - 任意の$k\in K$と任意の$\bm{x}\in V$に対して
\[ f(k\bm{x})=kf(\bm{x})\]
が成り立つ.
を満たすとき,$f$を線形写像(linear mapping)という.
定義1の2つの条件をまとめると,次のようになる.
任意の$k,l\in K$と$\bm{x},\bm{y}\in V$に対して
\[ f(k\bm{x}+l\bm{y})=kf(\bm{x})+lf(\bm{y})\]
が成り立つ.
定義から直ちに分かることとして,次の命題1を得る.
$K$を体,$V,W$を$K$上のベクトル空間,$f:V\to W$を線形写像とする.
\[ f(\bm{0}_V)=\bm{0}_W\]
\[ f(\bm{0}_V)=f(0\cdot \bm{0}_V)=0\cdot f(\bm{0}_V)=\bm{0}_W\quad \blacksquare \]
線形写像の例
重要な線形写像や,線形写像の具体例を紹介する.
$K$を体,$V,W$を$K$上のベクトル空間とする.
写像$f:V\to W$を
\[ f(\bm{x})=\bm{0}_W\quad (\bm{x}\in V)\]
により定めると,$f$は線形写像である.
まず,任意の$\bm{x},\bm{y}\in V$に対して
\[ \begin{aligned}f(\bm{x}+\bm{y})&=\bm{0}=\bm{0}+\bm{0}\\ &=f(\bm{x})+f(\bm{y})\end{aligned}\]
が成り立つ.
また,任意の$k\in K$と任意の$\bm{x}\in V$に対して
\[ f(k\bm{x})=\bm{0}=k\cdot \bm{0}=kf(\bm{x})\]
が成り立つ.
以上より,$f$は線形写像である.$\blacksquare$
補題1の線形写像には名前がついている.
$V,W$をベクトル空間とする.
\[ f(\bm{x})=\bm{0}_W\quad (\bm{x}\in V)\]
により定まる線形写像$f:V\to W$を零写像(または零線形写像)(zero map)(または零作用素(または零線形作用素)(zero operator))という.
また,定義域と終域が等しい線形写像は特に重要である.
$V$をベクトル空間とする.
線形写像$f:V\to V$を$V$の線形変換(linear transformation)(または1次変換)という.
線形変換の最もシンプルな例として,次の写像がある.
$V$をベクトル空間とする.
恒等写像$\mathrm{id}_V:V\to V$は線形変換である.
まず,任意の$\bm{x},\bm{y}\in V$に対して
\[ \mathrm{id}_V(\bm{x}+\bm{y})=\bm{x}+\bm{y}=\mathrm{id}_V(\bm{x})+\mathrm{id}_V(\bm{y})\]
が成り立つ.
また,任意の$k\in K$と任意の$\bm{x}\in V$に対して
\[ \mathrm{id}_V(k\bm{x})=k\bm{x}=k\mathrm{id}_V(\bm{x})\]
が成り立つ.
以上より,$\mathrm{id}_V$は線形写像である.$\blacksquare$
補題2の線形変換には名前がついている.
$V$をベクトル空間とする.
恒等写像$\mathrm{id}_V:V\to V$を特に恒等写像(identity mapping, identity function)(または恒等変換(identity transformation),恒等作用素(identity opeator))という.
$\mathbb{R}$上のベクトル空間$\mathbb{R}^2$に対して,写像$f:\mathbb{R}^2\to \mathbb{R}^2$を
\[ f(\mathbb{x})=\begin{pmatrix}1&-1\\ -1&1\end{pmatrix}\bm{x}\quad (\bm{x}\in \mathbb{R}^2)\]
により定めると,$f$は$\mathbb{R}^2$の線形変換である.
実際,$A=\begin{pmatrix}1&-1\\ -1&1\end{pmatrix}$とおくと,
任意の$\bm{x},\bm{y}\in \mathbb{R}^2$に対して
\[ \begin{aligned}&f(\bm{x}+\bm{y})=A(\bm{x}+\bm{y})\\ =&A\bm{x}+A\bm{y}=f(\bm{x})+f(\bm{y})\end{aligned}\]
であり,任意の$k\in \mathbb{R}$と$\bm{x}\in \mathbb{R}^2$に対して
\[ f(k\bm{x})=A(k\bm{x})=k(A\bm{x})=kf(\bm{x})\]
である.
例4について,次の興味深い定理1が成り立つ.
$m,n\in \mathbb{N}$,$K$を体,$\mathbb{R}^m\mathbb{R}^n$を$K$上のベクトル空間,$f:\mathbb{R}^n\to \mathbb{R}^m$を線形写像とする.
$K$上のある$m\times n$行列$A$が存在して
\[ f(\bm{x})=A\bm{x}\quad (\bm{x}\in \mathbb{R}^n)\]
となる.
$\{ \bm{e}_1,\bm{e}_2,\dots ,\bm{e}_n\}$を$\mathbb{R}^n$の標準基底,$\{ \bm{e}^{\prime}_1,\bm{e}^{\prime}_2,\dots ,\bm{e}^{\prime}_m\}$を$\mathbb{R}^m$の標準基底とする.
任意の$j\in \{ 1,2,\dots ,n\}$に対して,ある$a_{1j},a_{2j},\dots ,a_{mj}\in K$が存在して
\[ f(\bm{e}_j)=a_{1j}\bm{e}^{\prime}_1+a_{2j}\bm{e}^{\prime}_2+\dots +a_{mj}\bm{e}^{\prime}_m\]
となる.
ここで
\[ A\coloneqq \begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots &a_{1n}\\ a_{21}&a_{22}&\cdots &a_{2n}\\ \vdots &\vdots &\ddots &\vdots \\ a_{m1}&a_{m2}&\cdots &a_{mn}\end{pmatrix}\]
とおくと,任意の$\bm{x}=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots \\ x_n\end{pmatrix}\in \mathbb{R}^n$に対して
\[ \begin{aligned}f(\bm{x})&=f(x_1\bm{e}_1+x_2\bm{e}_2+\dots +x_n\bm{e}_n)\\ &=x_1f(\bm{e}_1)+x_2f(\bm{e}_2)+\dots +x_nf(\bm{e}_n)\\ &=x_1(a_{11}\bm{e}^{\prime}_1+a_{21}\bm{e}^{\prime}_2+\dots +a_{m1}\bm{e}^{\prime}_m)\\ &\quad +x_2(a_{12}\bm{e}^{\prime}_1+a_{22}\bm{e}^{\prime}_2+\dots +a_{m2}\bm{e}^{\prime}_m)\\ &\quad +\dots \\ &\quad +x_n(a_{1n}\bm{e}^{\prime}_1+a_{2n}\bm{e}^{\prime}_2+\dots +a_{mn}\bm{e}^{\prime}_m)\\ &=(a_{11}x_1+a_{12}x_2+\dots +a_{1n}x_n)\bm{e}^{\prime}_1\\ &\quad +(a_{21}x_1+a_{22}x_2+\dots +a_{2n}x_n)\bm{e}^{\prime}_2\\ &\quad +\dots \\ &\quad +(a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\dots +a_{mn}x_n)\bm{e}^{\prime}_m\\ &=E_m\begin{pmatrix}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\dots +a_{1n}x_n\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\dots +a_{2n}x_n\\ \vdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\dots +a_{mn}x_n\end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots &a_{1n}\\ a_{21}&a_{22}&\cdots &a_{2n}\\ \vdots &\vdots &\ddots &\vdots \\ a_{m1}&a_{m2}&\cdots &a_{mn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots \\ x_n\end{pmatrix}\\ &=A\bm{x}\end{aligned}\]
が成り立つ.$\blacksquare$
線形写像の像と核
線形写像から定義される,次の2つの集合は特に重要である.
$V,W$をベクトル空間,$f:V\to W$を線形写像とする.
- 集合
\[ \{ f(\bm{x})\in W\mid \bm{x}\in V\} \]
を$f$の像(image)といい,$\operatorname{Im}f$で表す. - 集合
\[ \{ \bm{x}\in V\mid f(\bm{x})=\bm{0}_W\} \]
を$f$の核(kernel)といい,$\operatorname{Ker}f$で表す.
$K$を体,$V,W$を$K$上のベクトル空間,$f:V\to W$を線形写像とする.
$\operatorname{Im}f$は$W$の部分空間である.
まず,命題1より
\[ \bm{0}_W=f(\bm{0}_V)\in \operatorname{Im}f\]
また,任意の$\bm{w}_1,\bm{w}_2\in \operatorname{Im}f$に対して,ある$\bm{v}_1,\bm{v}_2\in V$が存在して
\[ \bm{w}_1=f(\bm{v}_1),\quad \bm{w}_2=f(\bm{v}_2)\]
となり,このとき,$f$は線形写像であるから
\[ \begin{aligned}\bm{w}_1+\bm{w}_2&=f(\bm{v}_1)+f(\bm{v}_2)\\ &=f(\bm{v}_1+\bm{v}_2)\in \operatorname{Im}f\end{aligned}\]
さらに,任意の$\bm{w}\in \operatorname{Im}f$に対して,ある$\bm{v}\in V$が存在して
\[ \bm{w}=f(\bm{v})\]
となる.このとき,$f$は線形写像であるから,任意の$k\in K$に対して
\[ k\bm{w}=kf(\bm{v})=f(k\bm{v})\in \operatorname{Im}f\]
以上より,$\operatorname{Im}f$は$W$の部分空間である.$\blacksquare$
$K$を体,$V,W$を$K$上のベクトル空間,$f:V\to W$を線形写像とする.
$\operatorname{Ker}f$は$V$の部分空間である.
まず,命題1より
\[ f(\bm{0}_V)=\bm{0}_W\]
であるから,$\bm{0}_V\in \operatorname{Ker}f$
また,$f$は線形写像であるから,任意の$\bm{v}_1,\bm{v}_2\in \operatorname{Ker}f$に対して
\[ \begin{aligned}f(\bm{v}_1+\bm{v}_2)&=f(\bm{v}_1)+f(\bm{v}_2)\\ &=\bm{0}+\bm{0}=\bm{0}\end{aligned}\]
よって,$\bm{v}_1+\bm{v}_2\in \operatorname{Ker}f$
さらに,$f$は線形写像であるから,任意の$\bm{v}\in \operatorname{Ker}f$と任意の$k\in K$に対して
\[ f(k\bm{v})=kf(\bm{v})=\bm{0}\]
よって,$k\bm{v}\in \operatorname{Ker}f$
以上より,$\operatorname{Ker}f$は$V$の部分空間である.$\blacksquare$
次元定理
$K$を体,$V$を$K$上の有限次元ベクトル空間,$W$を$K$上のベクトル空間,$f:V\to W$を線形写像とする.
$\operatorname{Im}f$,$\operatorname{Ker}f$は有限次元ベクトル空間である.
$V$は有限次元ベクトル空間であるから,$n=\dim V$とすると,$V$の基底$\{ \bm{v}_1,\bm{v}_2,\dots ,\bm{v}_n\}$が存在する.
このとき,任意の$\bm{v}\in V$に対して,ある$k_1,k_2,\dots ,k_n\in K$が存在して
\[ \bm{v}=k_1\bm{v}_1+k_2\bm{v}_2+\dots +k_n\bm{v}_n\]
となり,$f$は線形写像であるから
\[ \begin{aligned}f(\bm{v})&=f(k_1\bm{v}_1+k_2\bm{v}_2+\dots +k_n\bm{v}_n)\\ &=k_1f(\bm{v}_1)+k_2f(\bm{v}_2)+\dots +k_nf(\bm{v}_n)\end{aligned}\]
よって
\[ W=\langle f(\bm{v}_1),f(\bm{v}_2),\dots ,f(\bm{v}_n)\rangle _K\]
であるから,$\operatorname{Im}f$は高々$n$次元のベクトル空間である.
また,命題3より,$\operatorname{Ker}f$は$V$の部分空間であるから,有限次元ベクトル空間である.$\blacksquare$
補題3より,線形写像の像と核の次元を考えることができる.
$V$を有限次元ベクトル空間,$W$を$V$の部分空間,$f:V\to W$を線形写像とする.
- $\dim (\operatorname{Im}f)$を$f$の階数(rank)といい,$\operatorname{rank}f$で表す.
- $\dim (\operatorname{Ker}f)$を$f$の退化次数(nullity)といい,$\operatorname{null}f$で表す.
このとき,次の定理2が成り立つ.
$K$を体,$V$を$K$上の有限次元ベクトル空間,$W$を$K$上のベクトル空間,$f:V\to W$を線形写像とする.
\[ \operatorname{rank}f+\operatorname{null}f=\dim V\]
$m=\operatorname{rank}f,n=\operatorname{null}f$とし,$\{ \bm{w}_1,\bm{w}_2,\dots ,\bm{w}_m\}$を$\operatorname{Im}f$の基底,$\{ \bm{v}_{m+1},\bm{v}_{m+2},\dots ,\bm{v}_{m+n}\}$を$\operatorname{Ker}f$の基底とする.
このとき,ある$\bm{v}_1,\bm{v}_2,\dots ,\bm{v}_n\in V$が存在して
\[ \bm{w}_1=f(\bm{v}_1),\bm{w}_2=f(\bm{v}_2),\dots ,\bm{w}_m=f(\bm{v}_m)\]
となる.
以下,$\{ \bm{v}_1,\bm{v}_2,\dots ,\bm{v}_{m+n}\}$が$V$の基底であることを示す.
$k_1,k_2,\dots ,k_{m+n}\in K$が
\[ k_1\bm{v}_1+k_2\bm{v}_2+\dots +k_{m+n}\bm{v}_{m+n}=\bm{0}_V\]
を満たすとき
\[ f(k_1\bm{v}_1+k_2\bm{v}_2+\dots +k_{m+n}\bm{v}_{m+n})=f(\bm{0}_V)\]
$f$が線形写像であることと,命題1を用いると
\[ k_1f(\bm{v}_1)+k_2f(\bm{v}_2)+\dots +k_{m+n}f(\bm{v}_{m+n})=\bm{0}_W\]
ここで
\[ f(\bm{v}_{m+1})=f(\bm{v}_{m+2})=\dots =f(\bm{v}_{m+n})=\bm{0}_W\]
であることに注意すると
\[ k_1\bm{w}_1+k_2\bm{w}_2+\dots +k_m\bm{w}_m=\bm{0}_W\]
$\bm{w}_1,\bm{w}_2,\dots ,\bm{w}_m$は1次独立であるから
\[ k_1=k_2=\dots =k_m=0\]
このとき
\[ k_{m+1}\bm{v}_{m+1}+k_{m+2}\bm{v}_{m+2}+\dots +k_{m+n}\bm{v}_{m+n}=\bm{0}_V\]
となる.$\bm{v}_{m+1},\bm{v}_{m+2},\dots ,\bm{v}_{m+n}$は1次独立であるから
\[ k_{m+1}=k_{m+2}=\dots =k_{m+n}=0\]
を得る.以上より,$\bm{v}_1,\bm{v}_2,\dots ,\bm{v}_{m+n}$は1次独立である.
また,任意の$\bm{v}\in V$に対して,ある$l_1,l_2,\dots ,l_m\in K$が存在して
\[ \begin{aligned}f(\bm{v})&=l_1\bm{w}_1+l_2\bm{w}_2+\dots +l_m\bm{w}_m\\ &=l_1f(\bm{v}_1)+l_2f(\bm{v}_2)+\dots +l_mf(\bm{v}_m)\\ &=f(l_1\bm{v}_1+l_2\bm{v}_2+\dots +l_m\bm{v}_m)\end{aligned}\]
となる.よって
\[ \begin{aligned}&f(\bm{v}-l_1\bm{v}_1-l_2\bm{v}_2-\dots -l_m\bm{v}_m)\\ =&f(\bm{v})-f(l_1\bm{v}_1+l_2\bm{v}_2+\dots +l_m\bm{v}_m)=\bm{0}\end{aligned}\]
であるから
\[ \bm{v}-l_1\bm{v}_1-l_2\bm{v}_2-\dots -l_m\bm{v}_m\in \operatorname{Ker}f\]
が従う.ゆえに,ある$l_{m+1},l_{m+2},\dots ,l_{m+n}\in K$が存在して
\[ \begin{aligned}&\bm{v}-l_1\bm{v}_1-l_2\bm{v}_2-\dots -l_m\bm{v}_m\\ =&l_{m+1}\bm{v}_{m+1}+l_{m+2}\bm{v}_{m+2}+\dots +l_{m+n}\bm{v}_{m+n}\end{aligned}\]
すなわち
\[ \bm{v}=l_1\bm{v}_1+l_2\bm{v}_2+\dots +l_{m+n}\bm{v}_{m+n}\]
を得る.したがって
\[ V=\langle \bm{v}_1,\bm{v}_2,\dots ,\bm{v}_{m+n}\rangle _K\]
以上より,$\{ \bm{v}_1,\bm{v}_2,\dots ,\bm{v}_{m+n}\}$は$V$の基底であるから
\[ \operatorname{rank}f+\operatorname{null}f=m+n=\dim V\quad \blacksquare \]
線形同型写像
最後に,2つのベクトル空間を同一視するために必要な条件について考えよう.
まず,ベクトル空間は集合であるから,2つのベクトル空間の間に1対1対応の関係,すなわち全単射が存在する必要がある.
また,ベクトル空間はただの集合ではなく,和とスカラー倍が定義されていて,それらの演算にはある種の整合性(交換律や結合律,分配律などの性質)が備わっている.そのため,演算の同一視が必要である.これは,線形写像の存在性と言い換えることができる.
例えば,ベクトル空間$V,W$とその間の線形写像$f:V\to W$に対して,$\bm{v},\bm{v}_1,\bm{v}_2\in V$と$\bm{w},\bm{w}_1,\bm{w}_2\in W$が
\[ f(\bm{v})=\bm{w}\\ f(\bm{v}_1)=\bm{w}_1\\ f(\bm{v}_2)=\bm{w}_2\]
で対応しているとき,線形写像の定義より,和については
\[ f(\bm{v}_1+\bm{v}_2)=f(\bm{v}_1)+f(\bm{v}_2)=\bm{w}_1+\bm{w}_2\]
で対応し,スカラー倍については
\[ f(k\bm{v})=kf(\bm{v})=k\bm{w}\]
で対応している(ただし,$k$はスカラー).
以上の議論により,2つのベクトル空間を同一視するためには,その間に全単射である線形写像が存在する必要があることが分かる.
$V,W$をベクトル空間,$f:V\to W$を線形写像とする.
- $f$が全射であるための必要十分条件は,$\operatorname{Im}f=W$である.
- $f$が単射であるための必要十分条件は,$\operatorname{Ker}f=\{ \bm{0}_V\}$である.
- まず,必要性を示す.
$\operatorname{Im}f\subset W$は明らかに成り立つ.
$f$は全射であるから,任意の$\bm{w}\in W$に対して,ある$\bm{v}\in V$が存在して,$f(\bm{v})=\bm{w}$となる.
よって,$W\subset \operatorname{Im}f$
以上より,$\operatorname{Im}f=W$
次に,十分性を示す.
$\operatorname{Im}f=W$より,任意の$\bm{w}\in W$に対して,$\bm{w}\in \operatorname{Im}f$であるから,ある$\bm{v}\in V$が存在して,$f(\bm{v})=\bm{w}$となる.
よって,$f$は全射である.$\blacksquare$ - まず,必要性を示す.
任意の$\bm{v}\in \operatorname{Ker}f$に対して,$f(\bm{v})=f(\bm{0}_V)=\bm{0}_W$が成り立つ.
$f$は単射であるから,$\bm{v}=\bm{0}_V$
よって,$\operatorname{Ker}f\subset \{ \bm{0}_V\}$
$\{ \bm{0}_V\} \subset \operatorname{Ker}f$
以上より,$\operatorname{Ker}f=\{ \bm{0}_V\}$
次に,十分性を示す.
任意の$\bm{v}_1,\bm{v}_2\in V$に対して,$f(\bm{v}_1)=f(\bm{v}_2)$ならば,$f$は線形写像であるから
\[ f(\bm{v}_1-\bm{v}_2)=f(\bm{v}_1)-f(\bm{v}_2)=\bm{0}_W\]
$\operatorname{Ker}f=\{ \bm{0}_V\}$より,$\bm{v}_1-\bm{v}_2=\bm{0}_V$
すなわち,$\bm{v}_1=\bm{v}_2$
よって,$f$は単射である.$\blacksquare$
2つのベクトル空間は,次のように同一視する.
$V,W$をベクトル空間とする.
全単射な線形写像$f:V\to W$が存在するとき,$V$と$W$は線形同型(または同型)(isomorphic)であるといい,$V\cong W$で表す.
また,$f$を線形同型写像(または同型写像)(isomorphism)という.
$K$を体,$V,W$を線形同型な$K$上のベクトル空間,$f:V\to W$を線形同型写像とする.
$f$の逆写像$f^{-1}:W\to V$は線形同型写像である.
まず,$f^{-1}$が線形写像であることを示す.
$f$は全射であるから,任意の$\bm{w}_1,\bm{w}_2\in W$に対して,ある$\bm{v}_1,\bm{v}_2\in V$が存在して,$f(\bm{v}_1)=\bm{w}_1,f(\bm{v}_2)=\bm{w}_2$となる.
$f$は線形写像であるから
\[ \begin{aligned}f(\bm{v}_1+\bm{v}_2)&=f(\bm{v}_1)+f(\bm{v}_2)\\ &=\bm{w}_1+\bm{w}_2\end{aligned}\]
よって
\[ \begin{aligned}f^{-1}(\bm{w}_1+\bm{w}_2)&=\bm{v}_1+\bm{v}_2\\ &=f^{-1}(\bm{w}_1)+f^{-1}(\bm{w}_2)\end{aligned}\]
となる.
また,$f$は全射であるから,任意の$\bm{w}\in W$に対して,ある$\bm{v}\in V$が存在して,$f(\bm{v})=\bm{w}$となる.
$f$は線形写像であるから
\[ f(k\bm{v})=kf(\bm{v})=k\bm{w}\]
このとき,任意の$k\in K$に対して
\[ f^{-1}(k\bm{w})=k\bm{w}=kf^{-1}(\bm{v})\]
となる.
以上より,$f^{-1}$は線形写像である.
一般に,全単射の逆写像も全単射であるから,$f^{-1}$は全単射な線形写像,すなわち線形同型写像である.$\blacksquare$