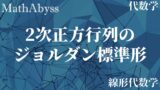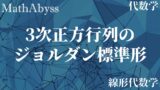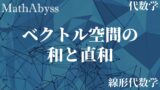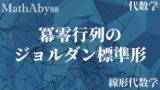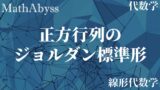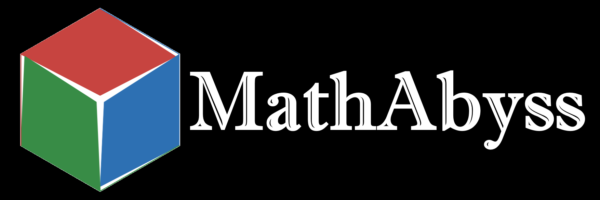ベクトル空間の基底の取り方に行列を対応付けることができたように,線形写像にも行列を対応付けることができる.
表現行列の定義
表現行列を定義する準備として,線形写像に行列を対応付けできることを示す.
$K$を体,$V,W$を$K$上の有限次元ベクトル空間,$f:V\to W$を線形写像,$n=\dim V,m=\dim W$,$\{ \bm{v}_1,\bm{v}_2,\dots ,\bm{v}_n\}$を$V$の基底,$\{ \bm{w}_1,\bm{w}_2,\dots ,\bm{w}_m\}$を$W$の基底とする.
ある$m\times n$行列$A$がただ一つ存在して
\[ \begin{pmatrix}f(\bm{v}_1)&f(\bm{v}_2)&\cdots &f(\bm{v}_n)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\bm{w}_1&\bm{w}_2&\cdots &\bm{w}_m\end{pmatrix}A\]
となる.
ある$a_{11},a_{12},\dots ,a_{mn}\in K$が一意に存在して
\[ f(\bm{v}_1)=a_{11}\bm{w}_1+a_{21}\bm{w}_2+\dots +a_{m1}\bm{w}_m\\ f(\bm{v}_2)=a_{12}\bm{w}_1+a_{22}\bm{w}_2+\dots +a_{m2}\bm{w}_m\\ \vdots \\ f(\bm{v}_n)=a_{1n}\bm{w}_1+a_{2n}\bm{w}_2+\dots +a_{mn}\bm{w}_m\]
となるから
\[ A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots &a_{1n}\\ a_{21}&a_{22}&\cdots &a_{2n}\\ \vdots &\vdots &\ddots &\vdots \\ a_{m1}&a_{m2}&\cdots &a_{mn}\end{pmatrix}\]
とおくと
\[ \begin{pmatrix}f(\bm{v}_1)&f(\bm{v}_2)&\cdots &f(\bm{v}_n)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\bm{w}_1&\bm{w}_2&\cdots &\bm{w}_m\end{pmatrix}A\]
となる.$\blacksquare$
補題1により,線形写像に対応する行列を一意的に定めることができる.これを表現行列として定義する.
$K$を体,$V,W$を$K$上の有限次元ベクトル空間,$f:V\to W$を線形写像,$n=\dim V,m=\dim W$,$\{ \bm{v}_1,\bm{v}_2,\dots ,\bm{v}_n\}$を$V$の基底,$\{ \bm{w}_1,\bm{w}_2,\dots ,\bm{w}_m\}$を$W$の基底とする.
等式
\[ \begin{pmatrix}f(\bm{v}_1)&f(\bm{v}_2)&\cdots &f(\bm{v}_n)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\bm{w}_1&\bm{w}_2&\cdots &\bm{w}_m\end{pmatrix}A\]
を満たす$K$上の$m\times n$行列$A$を,基底$\{ \bm{v}_1,\bm{v}_2,\dots ,\bm{v}_n\}$,$\{ \bm{w}_1,\bm{w}_2,\dots ,\bm{w}_m\}$に関する$f$の表現行列(representation matrix)という.
特に,$f$が$V$の線形変換,すなわち$V=W$であるとき,基底$\{ \bm{v}_1,\bm{v}_2,\dots ,\bm{v}_n\}$,$\{ \bm{v}_1,\bm{v}_2,\dots ,\bm{v}_n\}$に関する$f$の表現行列を,基底$\{ \bm{v}_1,\bm{v}_2,\dots ,\bm{v}_n\}$に関する$f$の表現行列という.
具体例で確認しよう.
$\mathbb{R}$上のベクトル空間$\mathbb{R}^2$の線形変換$f:\mathbb{R}^2\to \mathbb{R}^2$を
\[ f(\bm{x})=\begin{pmatrix}1&2\\ -2&0\end{pmatrix}\bm{x}\quad (\bm{x}\in \mathbb{R}^2)\]
により定める.
\[ \bm{a}=\begin{pmatrix}-2\\ 1\end{pmatrix},\bm{b}=\begin{pmatrix}1\\ 3\end{pmatrix}\]
とおくと,$\{ \bm{a},\bm{b}\}$は$\mathbb{R}^2$の基底である.この基底に関する$f$の表現行列を求める.
\[ \begin{aligned}f(\bm{a})&=\begin{pmatrix}1&2\\ -2&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2\\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 4\end{pmatrix}\\ &=\frac{4}{7}\bm{a}+\frac{8}{7}\bm{b}\end{aligned}\]
\[ \begin{aligned}f(\bm{b})&=\begin{pmatrix}1&2\\ -2&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7\\ -2\end{pmatrix}\\ &=-\frac{23}{7}\bm{a}+\frac{3}{7}\bm{b}\end{aligned}\]
であるから,表現行列は
\[ \frac{1}{7}\begin{pmatrix}4&-23\\ 8&3\end{pmatrix}\]
表現行列とベクトルの成分
線形写像の表現行列の威力は,次の定理1が成り立つことである.
$K$を体,$V,W$を$K$上の有限次元ベクトル空間,$f:V\to W$を線形写像,$n=\dim V,m=\dim W$,$\{ \bm{v}_1,\bm{v}_2,\dots ,\bm{v}_n\}$を$V$の基底,$\{ \bm{w}_1,\bm{w}_2,\dots ,\bm{w}_m\}$を$W$の基底,$A$を基底$\{ \bm{v}_1,\bm{v}_2,\dots ,\bm{v}_n\}$,$\{ \bm{w}_1,\bm{w}_2,\dots ,\bm{w}_m\}$に関する$f$の表現行列とする.
また,$\bm{v}\in V$,$x_1,x_2,\dots ,x_n\in K$を基底$\{ \bm{v}_1,\bm{v}_2,\dots ,\bm{v}_n\}$に関する$\bm{v}$の成分,$y_1,y_2,\dots ,y_m\in K$を基底$\{ \bm{w}_1,\bm{w}_2,\dots ,\bm{w}_m\}$に関する$\bm{v}$の成分とする.
\[ \begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ \vdots \\ y_m\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots \\ x_n\end{pmatrix}\]
まず
\[ f(\bm{v})=\begin{pmatrix}\bm{w}_1&\bm{w}_2&\cdots &\bm{w}_m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ \vdots \\ y_n\end{pmatrix}\]
また
\[ \begin{aligned}f(\bm{v})&=f(x_1\bm{v}_1+x_2\bm{v}_2+\dots +x_n\bm{v}_n)\\ &=x_1f(\bm{v}_1)+x_2f(\bm{v}_2)+\dots +x_nf(\bm{v}_n)\\ &=\begin{pmatrix}f(\bm{v}_1)&f(\bm{v}_2)&\cdots &f(\bm{v}_n)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots \\ x_n\end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix}\bm{w}_1&\bm{w}_2&\cdots &\bm{w}_m\end{pmatrix}A\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots \\ x_n\end{pmatrix}\end{aligned}\]
よって
\[ \begin{aligned}&\begin{pmatrix}\bm{w}_1&\bm{w}_2&\cdots &\bm{w}_m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ \vdots \\ y_n\end{pmatrix}\\ =&\begin{pmatrix}\bm{w}_1&\bm{w}_2&\cdots &\bm{w}_m\end{pmatrix}A\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots \\ x_n\end{pmatrix}\end{aligned}\]
$\{ \bm{w}_1,\bm{w}_2,\dots ,\bm{w}_m\}$は$W$の基底であるから,$\bm{w}_1,\bm{w}_2,\dots ,\bm{w}_m$は1次独立,すなわち
\[ \begin{pmatrix}\bm{w}_1&\bm{w}_2&\cdots &\bm{w}_m\end{pmatrix}\]
は正則であることに注意すると,両辺に左から
\[ \begin{pmatrix}\bm{w}_1&\bm{w}_2&\cdots &\bm{w}_m\end{pmatrix}^{-1}\]
を掛けて
\[ \begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ \vdots \\ y_m\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots \\ x_n\end{pmatrix}\]
を得る.$\blacksquare$
定理1より,線形写像によってベクトルがうつる先は,行列の積によって計算できる.
$\mathbb{R}$上のベクトル空間$\mathbb{R}^2$の線形変換$f:\mathbb{R}^2\to \mathbb{R}^2$を
\[ f(\bm{x})=\begin{pmatrix}1&2\\ -2&0\end{pmatrix}\bm{x}\quad (\bm{x}\in \mathbb{R}^2)\]
により定める.
基底
\[ \left\{ \begin{pmatrix}-2\\ 1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\ 3\end{pmatrix}\right\} \]
に関する$f$の表現行列は
\[ \frac{1}{7}\begin{pmatrix}4&-23\\ 8&3\end{pmatrix}\]
である(例1).
\[ \bm{a}=\begin{pmatrix}-2\\ 1\end{pmatrix},\bm{b}=\begin{pmatrix}1\\ 3\end{pmatrix}\]
とおくと
\[ \frac{1}{7}\begin{pmatrix}4&-23\\ 8&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\ -3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}11\\ 1\end{pmatrix}\]
であるから,定理1より
\[ f(2\bm{a}-3\bm{b})=11\bm{a}+\bm{b}\]
表現行列と基底変換
表現行列は,ベクトル空間の基底の取り方に依存して決まる.基底変換によって表現行列がどのように変わるかを与えるのが,次の定理2である.
$K$を体,$V,W$を$K$上の有限次元ベクトル空間,$f:V\to W$を線形写像,$n=\dim V,m=\dim W$,$\{ \bm{v}_1,\bm{v}_2,\dots ,\bm{v}_n\} ,\{ \bm{v}^{\prime}_1,\bm{v}^{\prime}_2,\dots ,\bm{v}^{\prime}_n\}$を$V$の基底,$\{ \bm{w}_1,\bm{w}_2,\dots ,\bm{w}_m\} ,\{ \bm{w}^{\prime}_1,\bm{w}^{\prime}_2,\dots ,\bm{w}^{\prime}_m\}$を$W$の基底,$A$を基底$\{ \bm{v}_1,\bm{v}_2,\dots ,\bm{v}_n\}$,$\{ \bm{w}_1,\bm{w}_2,\dots ,\bm{w}_m\}$に関する$f$の表現行列,$B$を基底$\{ \bm{v}^{\prime}_1,\bm{v}^{\prime}_2,\dots ,\bm{v}^{\prime}_n\}$,$\{ \bm{w}^{\prime}_1,\bm{w}^{\prime}_2,\dots ,\bm{w}^{\prime}_m\}$に関する$f$の表現行列,$P$を基底変換
\[ \{ \bm{v}_1,\bm{v}_2,\dots ,\bm{v}_n\} \to \{ \bm{v}^{\prime}_1,\bm{v}^{\prime}_2,\dots ,\bm{v}^{\prime}_n\} \]
の基底変換行列,$Q$を基底変換
\[ \{ \bm{w}_1,\bm{w}_2,\dots ,\bm{w}_m\} \to \{ \bm{w}^{\prime}_1,\bm{w}^{\prime}_2,\dots ,\bm{w}^{\prime}_m\} \]
の基底変換行列とする.
\[ B=Q^{-1}AP\]
$i,j\in \{ 1,2,\dots ,n\}$,$p_{ij}\in K$を$P$の$(i,j)$成分とする.
まず
\[ \begin{aligned}&\begin{pmatrix}f(\bm{v}^{\prime}_1)&f(\bm{v}^{\prime}_2)&\cdots &f(\bm{v}^{\prime}_n)\end{pmatrix}\\ =&\begin{pmatrix}\bm{w}^{\prime}_1&\bm{w}^{\prime}_2&\cdots &\bm{w}^{\prime}_m\end{pmatrix}B\\ =&\begin{pmatrix}\bm{w}_1&\bm{w}_2&\cdots &\bm{w}_m\end{pmatrix}QB\end{aligned}\]
また
\[ \begin{aligned}&\begin{pmatrix}f(\bm{v}^{\prime}_1)&f(\bm{v}^{\prime}_2)&\cdots &f(\bm{v}^{\prime}_n)\end{pmatrix}\\ =&\begin{pmatrix}f(p_{11}\bm{v}_1+\dots +p_{n1}\bm{v}_n)&\cdots &f(p_{1n}\bm{v}_1+\dots +p_{nn}\bm{v}_n)\end{pmatrix}\\ =&\begin{pmatrix}p_{11}f(\bm{v}_1)+\dots +p_{n1}f(\bm{v}_n)&\cdots &p_{1n}f(\bm{v}_1)+\dots +p_{nn}f(\bm{v}_n)\end{pmatrix}\\ =&\begin{pmatrix}f(\bm{v}_1)&f(\bm{v}_2)&\cdots &f(\bm{v}_n)\end{pmatrix}P\\ =&\begin{pmatrix}\bm{w}_1&\bm{w}_2&\cdots &\bm{w}_m\end{pmatrix}AP\end{aligned}\]
よって
\[ \begin{pmatrix}\bm{w}_1&\bm{w}_2&\cdots &\bm{w}_m\end{pmatrix}QB=\begin{pmatrix}\bm{w}_1&\bm{w}_2&\cdots &\bm{w}_m\end{pmatrix}AP\]
$\{ \bm{w}_1,\bm{w}_2,\dots ,\bm{w}_m\}$は$W$の基底であるから,$\bm{w}_1,\bm{w}_2,\dots ,\bm{w}_m$は1次独立,すなわち
\[ \begin{pmatrix}\bm{w}_1&\bm{w}_2&\cdots &\bm{w}_m\end{pmatrix}\]
は正則であることに注意する.$Q$も正則であり,両辺に左から
\[ Q^{-1}\begin{pmatrix}\bm{w}_1&\bm{w}_2&\cdots &\bm{w}_m\end{pmatrix}^{-1}\]
を掛けて
\[ B=Q^{-1}AP\]
を得る.$\blacksquare$
特に,線形変換の場合は重要である.
$K$を体,$V$を$K$上の有限次元ベクトル空間,$f:V\to V$を線形変換,$n=\dim V$,$\{ \bm{v}_1,\bm{v}_2,\dots ,\bm{v}_n\} ,\{ \bm{v}^{\prime}_1,\bm{v}^{\prime}_2,\dots ,\bm{v}^{\prime}_n\}$を$V$の基底,$A$を基底$\{ \bm{v}_1,\bm{v}_2,\dots ,\bm{v}_n\}$に関する$f$の表現行列,$B$を基底$\{ \bm{v}^{\prime}_1,\bm{v}^{\prime}_2,\dots ,\bm{v}^{\prime}_n\}$に関する$f$の表現行列,$P$を基底変換
\[ \{ \bm{v}_1,\bm{v}_2,\dots ,\bm{v}_n\} \to \{ \bm{v}^{\prime}_1,\bm{v}^{\prime}_2,\dots ,\bm{v}^{\prime}_n\} \]
の基底変換行列とする.
\[ B=P^{-1}AP\]
これは,定理1で
\[ W=V\\ \{ \bm{w}_1,\bm{w}_2,\dots ,\bm{w}_m\} =\{ \bm{v}_1,\bm{v}_2,\dots ,\bm{v}_n\} \\ \{ \bm{w}^{\prime}_1,\bm{w}^{\prime}_2,\dots ,\bm{w}^{\prime}_m\} =\{ \bm{v}^{\prime}_1,\bm{v}^{\prime}_2,\dots ,\bm{v}^{\prime}_n\} \\ Q=P\]
としたものに他ならない.
よって,$B=P^{-1}AP$が成り立つ.$\blacksquare$
線形写像の表現行列を考えることで,写像によってベクトルがうつる先は,行列の積で機械的に計算することが可能となった.特に,表現行列は基底の取り方に依存するため,うまく基底を選べば,行列の積が容易に計算できるような「良い性質」を持つ表現行列を求めることができる.
この「良い性質」を持つ行列は,対角行列やジョルダン標準形であり,このような行列を求めることが次の目標となる.
対角行列については,次の記事で詳しく解説している.
ジョルダン標準形については,次の記事で詳しく解説している.