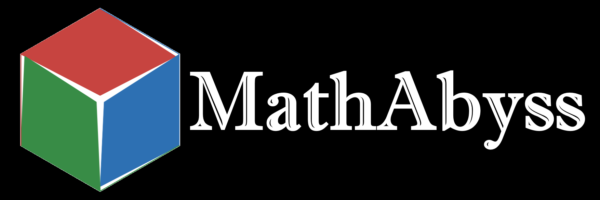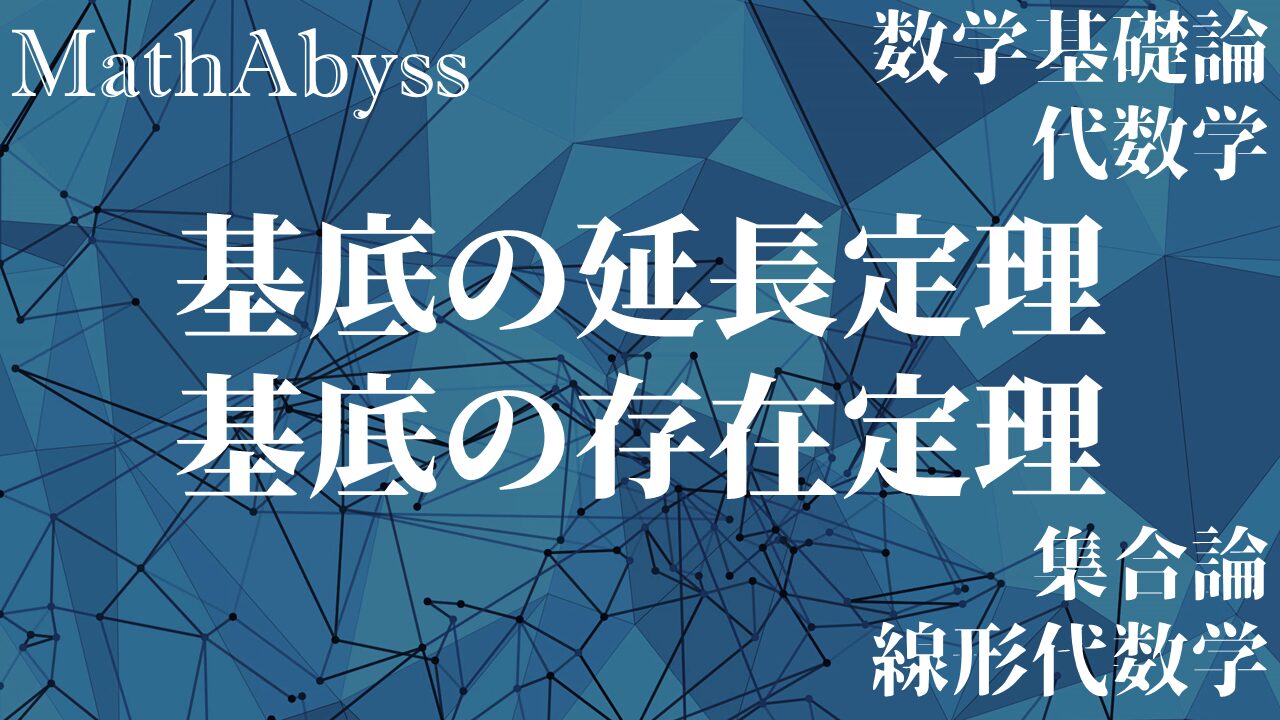零空間でない任意のベクトル空間に対して,基底が存在することを示す.
基底の延長定理
部分空間の基底にいくつかベクトルを付け加えることで,元のベクトル空間の基底を構成できる.
$m,n\in \mathbb{N}$は$m<n$を満たし,$K$を体,$V$を$K$上の$n$次元ベクトル空間,$W$を$V$の$m$次元部分空間,$\{ \bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_m\}$を$W$の基底とする.
ある$\bm{x}_{m+1},\bm{x}_{m+2},\dots ,\bm{x}_n\in V$が存在して,$\{ \bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_n\}$は$V$の基底となる.
$\bm{x}_{m+1},\bm{x}_{m+2},\dots ,\bm{x}_n\in V$を,帰納的に
\[ \bm{x}_{m+i}\in V\setminus \langle \bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_{m+i-1}\rangle _K\quad (i\in \{ 1,2,\dots ,n-m\})\]
で定める.
ただし,任意の$i\in \{ 1,2,\dots ,n-m\}$に対して
\[ \langle \bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_{m+i-1}\rangle _K\]
の次元は高々$m+i-1$であるから
\[ V\setminus \langle \bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_{m+i-1}\rangle _K\]
は空でないことに注意する.
このとき,$\bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_{m+i}$は1次独立であることを示す.
ある$k_1,k_2,\dots ,k_{m+i}\in K$が
\[ k_1\bm{x}_1+k_2\bm{x}_2+\dots +k_{m+i-1}\bm{x}_{m+i-1}+k_{m+i}\bm{x}_{m+i}=\bm{0}\]
を満たすとき
\[ k_{m+i}\bm{x}_{m+i}=-k_1\bm{x}_1-k_2\bm{x}_2-\dots -k_{m+i-1}\bm{x}_{m+i-1}\in W\]
となるが,$\bm{x}_{m+i}\not\in W$であるから,$k_{m+i}=0$
よって
\[ k_1\bm{x}_1+k_2\bm{x}_2+\dots +k_{m+i-1}\bm{x}_{m+i-1}=\bm{0}\]
であり,$\bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_{m+i-1}$は1次独立であるから
\[ k_1=k_2=\dots =k_{m+i-1}=0\]
を得る.
以上より,$\langle \bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_{m+i}\rangle _K$は$V$の部分空間であり,その次元は$m+i$である.
したがって,$\bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_n$は1次独立となるから,$\dim V=n$より,$\{ \bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_n\}$は$V$の基底である.$\blacksquare$
基底の存在定理
有限次元ベクトル空間は,零空間に加え,有限個のベクトルの組を基底に持つベクトル空間のことであった.そのため,零空間でない有限次元ベクトル空間に基底が存在することは,定義より明らかである.
実は,無限次元ベクトル空間にも基底が存在することが証明できる.
零空間でない任意のベクトル空間に対して,その基底が存在することを証明するには,選択公理を認める必要がある.
$\{ X_\lambda \} _{\lambda \in \Lambda}$を$\Lambda$を添字集合とする集合族とする.
任意の$\lambda \in \Lambda$に対して,$X_{\lambda}\neq \emptyset$ならば
\[ \prod _{\lambda \in \Lambda}X_{\lambda}\neq \emptyset \]
選択公理と同値な命題として,ツォルンの補題がある.
帰納的順序集合は極大元を持つ.
詳しくは,次の記事を参照するとよい.
基底の存在定理の証明には,ツォルンの補題を用いる必要がある.
零空間でない任意のベクトル空間は基底を持つ.
$V$を零空間でないベクトル空間とする.
集合族$B$を
\[ B\coloneqq \{ S\subset V\mid \forall \bm{x}\in S,\forall \bm{y}\in S,\bm{x}\neq \bm{y}\implies \bm{x}と\bm{y}は1次独立\} \]
により定める.
$V$は零空間でないから,$\bm{v}\in V\setminus \{ \bm{0}\}$が存在する.このとき,$\bm{v}$は1次独立であるから,$\{ \bm{v}\} \in B$
よって,$B$は空でない.
また,$B$は集合の包含関係に関して順序集合である.
$B$の任意の全順序部分集合$A$に対して
\[ A^{\prime}\coloneqq \bigcup _{S\in A}S\]
とおくと,任意の$S\in A$に対して,$S\subset A^{\prime}$である.
このとき,$A^{\prime}\in B$であることを示す.
実際,任意の$\bm{v}_1,\bm{v}_2\in A^{\prime}$に対して,ある$S_1,S_2\in A$が存在して,$\bm{v}_1\in S_1$かつ$\bm{v}_2\in S_2$となる.
$A$は全順序集合であるから,ある$S^{\prime}\in A$が存在して,$S_1\cup S_2\subset S^{\prime}$となる.
よって,$\bm{v}_1,\bm{v}_2\in S^{\prime}$であるから,$\bm{v}_1,\bm{v}_2$は1次独立,すなわち$A^{\prime}\in B$であるから,$A^{\prime}$は$A$の上界であり,$B$は帰納的である.
したがって,ツォルンの補題より,$B$の極大元$B^{\prime}$が存在する.
このとき,$B^{\prime}$が$V$の基底であることを示す.
ある$\bm{v}_0\in V$が存在して,$\bm{v}_0$が$B^{\prime}$の有限個の元の1次結合で表されないと仮定する.
異なる$\bm{w}_1,\bm{w}_2\in B^{\prime}\cup \bm{v}_0$を任意にとる.
$\bm{w}_1,\bm{w}_2\in B^{\prime}$のとき,$B^{\prime}\subset B$であるから,$\bm{w}_1$と$\bm{w}_2$は1次独立である.
$\bm{w}_1=\bm{v}_0$かつ$\bm{w}_2\in B^{\prime}$であるとき,$k_1,k_2\in K$が
\[ k_1\bm{v}_0+k_2\bm{w}_2=\bm{0}\]
を満たすとき,ある$n\in \mathbb{N}$と$l_1,l_2,\dots ,l_n\in K$,相異なる$\bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_n\in B^{\prime}$が存在して
\[ \bm{w}_2=l_1\bm{x}_1+l_2\bm{x}_2+\dots +l_n\bm{x}_n\]
となる.よって
\[ \begin{aligned}k_1\bm{v}_0&=-k_2(l_1\bm{x}_1+l_2\bm{x}_2+\dots +l_n\bm{x}_n)\\ &=-k_2l_1\bm{x}_1-k_2l_2\bm{x}_2-\dots -k_2l_n\bm{x}_n\end{aligned}\]
仮定より$k_1=0$であるから
\[ k_2\bm{w}_2=\bm{0}\]
$\bm{w}_2\neq \bm{0}$に注意すると,$k_2=0$
よって,$\bm{w}_1=\bm{v}_0,\bm{w}_2$は1次独立である.
以上より,$B^{\prime}\cup \{ \bm{v}_0\} \in B$である.
$B^{\prime}\subsetneq B^{\prime}\cup \{ \bm{v}_0\}$であるから,これは$B^{\prime}$が$B$の極大元であることに矛盾する.
したがって,任意の$V$の元は$B^{\prime}$の有限個の元の1次結合で表されるから,$B^{\prime}$は$V$の基底である.$\blacksquare$
この記事では証明を割愛するが1,正則性公理を用いると,基底の存在定理から選択公理を導くことができ,選択公理と基底の存在定理が同値であることを示すことができる.
- いつかこの記事に証明を掲載するかもしれない. ↩︎