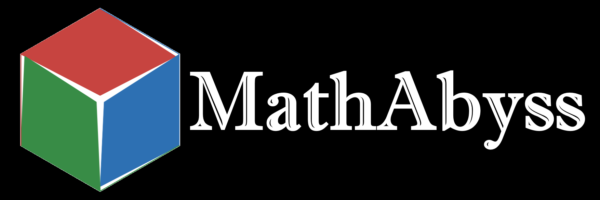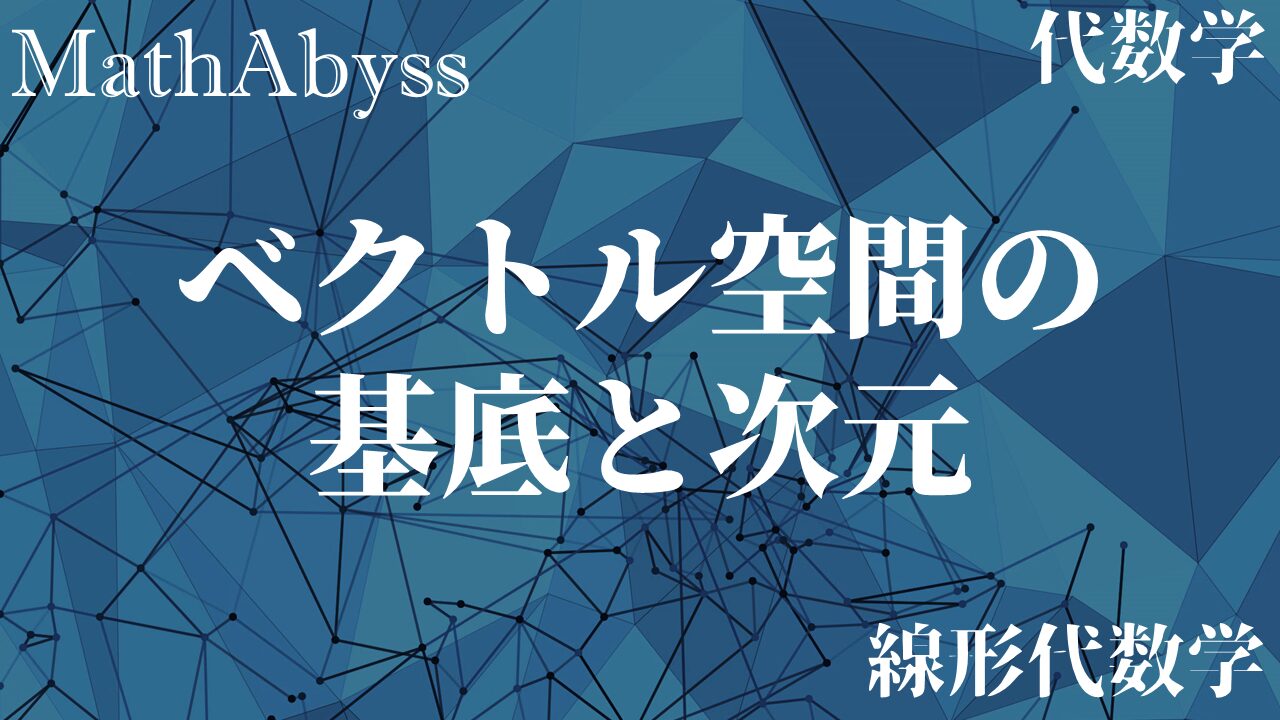ベクトル空間を特徴づける概念として,基底と次元を定義する.
ベクトル空間の生成
いくつかのベクトルが与えられたとき,それらの1次関係で表されるベクトル全体の集合はベクトル空間になる.
$n\in \mathbb{N}$,$K$を体,$V$を$K$上のベクトル空間,$\bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_n\in V$とする.
$V$の部分集合
\[ W=\{ k_1\bm{x}_1+k_2\bm{x}_2+\dots +k_n\bm{x}_n\mid k_1,k_2,\dots ,k_n\in K\} \]
は$V$の部分空間である.
まず,$\bm{0}\in W$を示す.
$0\in K$であるから
\[ \bm{0}=0\bm{x}_1+0\bm{x}_2+\dots +0\bm{x}_n\in W\]
ここで,$\bm{x},\bm{y}\in W$を任意にとる.
このとき,ある$k_1,k_2,\dots ,k_n,l_1,l_2,\dots ,l_n\in K$が存在して
\[ \begin{aligned}\bm{x}&=k_1\bm{x}_1+k_2\bm{x}_2+\dots +k_n\bm{x}_n\\ \bm{y}&=l_1\bm{x}_1+l_2\bm{x}_2+\dots +l_n\bm{x}_n\end{aligned}\]
となる.
次に,$\bm{x}+\bm{y}\in W$であることを示す.
\[ \begin{aligned}\bm{x}+\bm{y}&=k_1\bm{x}_1+k_2\bm{x}_2+\dots +k_n\bm{x}_n\\ &\qquad +l_1\bm{x}_1+l_2\bm{x}_2+\dots +l_n\bm{x}_n\\ &=(k_1+l_1)\bm{x}_1+(k_2+l_2)\bm{x}_2+\dots +(k_n+l_n)\bm{x}_n\end{aligned}\]
$k_1+l_1,k_2+l_2,\dots ,k_n+l_n\in K$であるから
\[ \bm{x}+\bm{y}\in W\]
最後に,$k\in K$に対して,$k\bm{x}\in W$であることを示す.
\[ \begin{aligned}k\bm{x}&=k(k_1\bm{x}_1+k_2\bm{x}_2+\dots +k_n\bm{x}_n)\\ &=kk_1\bm{x}_1+kk_2\bm{x}_2+\dots +kk_n\bm{x}_n\end{aligned}\]
$kk_1,kk_2,\dots ,kk_n\in K$であるから
\[ k\bm{x}\in W\]
以上より,$W$は$V$の部分空間である.$\blacksquare$
補題1の部分空間には名前がついている.
$n\in \mathbb{N}$,$K$を体,$V$を$K$上のベクトル空間,$\bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_n\in V$とする.
$V$の部分集合
\[ \{ k_1\bm{x}_1+k_2\bm{x}_2+\dots +k_n\bm{x}_n\mid k_1,k_2,\dots ,k_n\in K\} \]
を$\bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_n$で生成される(または張られる)$V$の部分空間といい
\[ \langle \bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_n\rangle _{K}\]
で表す.
実は,逆に任意のベクトル空間はいくつかのベクトルによって生成される1.そのようなベクトルの組について,次節で考える.
ベクトル空間の基底
一般に,ベクトル空間にはたくさんの元が存在する.そこで,これらのベクトルをより少ない(特に有限個の)ベクトルのみを用いて扱いたい.これは,ベクトル空間を生成するベクトルの組を考えればよく,$\mathbb{R}^3$の$xyz$直交座標のように,ベクトル空間に座標軸を設定するというイメージで捉えるとよい..
$n\in \mathbb{N}$,$K$を体,$V$を$K$上のベクトル空間,$\bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_n\in V$とする.
$\bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_n$が次の2つの条件
- $\bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_n$は1次独立である.
- $V=\langle \bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_n\rangle _{K}$
を満たすとき,$\{ \bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_n\}$を$V$の基底(basis)という.
$K$を体,$V$を$K$上のベクトル空間,$\bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots \in V$とする.
$\bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots$が次の2つの条件
- 任意の$m,n\in \mathbb{N}$に対して,$m\neq n$ならば$\bm{x}_m,\bm{x}_n$は1次独立である.
- 任意の$\bm{x}\in V$は,$\bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots$のうち,有限個のベクトルの1次結合で表される.
を満たすとき,$\{ \bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots \}$を$V$の基底(basis)という.
具体例で確認しよう.
$n\in \mathbb{N}$とする.
$\{ \bm{e}_1,\bm{e}_2,\dots ,\bm{e}_n\}$は$\mathbb{R}$上のベクトル空間$\mathbb{R}^n$の基底である.
実際,$\bm{e}_1,\bm{e}_2,\dots ,\bm{e}_n$は1次独立である2.
また,任意の$\bm{x}=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots \\ x_n\end{pmatrix}\in \mathbb{R}^n$に対して
\[ \bm{x}=x_1\bm{e}_1+x_2\bm{e}_2+\dots +x_n\bm{e}_n\]
が成り立つから
\[ \mathbb{R}^n=\langle \bm{e}_1,\bm{e}_2,\dots ,\bm{e}_n\rangle _{\mathbb{R}}\]
である.
例1の基底には名前がついている.
$n\in \mathbb{N}$,$\mathbb{R}^n$を$\mathbb{R}$上のベクトル空間とする.
$\{ \bm{e}_1,\bm{e}_2,\dots ,\bm{e}_n\}$を$\mathbb{R}^n$の標準基底(standard basis, canonical basis)(または自然基底(natural basis))という.
標準基底以外の基底も存在する.
$\begin{pmatrix}2\\ 1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\ 1\end{pmatrix}\in \mathbb{R}^2$は$\mathbb{R}^2$の基底である.
まず,$\begin{pmatrix}2\\ 1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\ 1\end{pmatrix}$は1次独立である.実際
\[ \begin{vmatrix}2&-1\\ 1&1\end{vmatrix}=2\cdot 1-(-1)\cdot 1=3\]
である3.
また
\[ \mathbb{R}^2=\left\langle \begin{pmatrix}2\\ 1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\ 1\end{pmatrix}\right\rangle _{\mathbb{R}}\]
である.実際,任意の$\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}\in \mathbb{R}^2$に対して
\[ a=\frac{1}{3}(x+y),b=\frac{1}{3}(-x+2y)\in \mathbb{R}\]
とおくと
\[ \begin{aligned}a\begin{pmatrix}2\\ 1\end{pmatrix}+b\begin{pmatrix}-1\\ 1\end{pmatrix}&=\begin{pmatrix}2a-b\\ a+b\end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix}\frac{2}{3}(x+y)-\frac{1}{3}(-x+2y)\\ \frac{1}{3}(x+y)+\frac{1}{3}(-x+2y)\end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}\end{aligned}\]
であるから
\[ \begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}\in \left\langle \begin{pmatrix}2\\ 1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\ 1\end{pmatrix}\right\rangle _{\mathbb{R}}\]
となる.
ベクトル空間の基底の取り方は一意的ではなく,様々な取り方が存在する.例えば,$\mathbb{R}^2$の基底として,標準基底を取ったり,例2のような基底を取ることができる.
ベクトル空間の次元
実は,ベクトル空間に対して,どのような基底を取ったとしても,基底を構成するベクトルの個数は不変である.
ベクトル空間の基底を構成するベクトルの個数は,基底の取り方に依らない.
$m,n\in \mathbb{N}$,$K$を体,$V$を$K$上のベクトル空間とする.
$V$が定義2の基底を持つときについてのみ考えればよい.
$\{ \bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_m\}$を$V$の基底,$\bm{y}_1,\bm{y}_2,\dots ,\bm{y}_n\in V$とする.
以下,$m<n$ならば,$\bm{y}_1,\bm{y}_2,\dots ,\bm{y}_n$は1次従属であることを,$m$に関する数学的帰納法で示す.
$m=1$のとき,$\{ \bm{x}_1\}$は$V$の基底であるから,ある$k_1,k_2\in K$が存在して
\[ \bm{y}_1=k_1\bm{x}_1,\quad \bm{y}_2=k_2\bm{x}_1\]
となる.
$k_1=k_2=0$のとき,$\bm{y}_1=\bm{y}_2=\bm{0}$となるから,$\bm{y}_1,\bm{y}_2$は1次従属である.
$k_1k_2\neq 0$のとき,非自明な1次関係
\[ k_2\bm{y}_1-k_1\bm{y}_2=k_2k_1\bm{x}_1-k_1k_2\bm{x}_2=\bm{0}\]
が成り立つから,$\bm{y}_1,\bm{y}_2$は1次従属である.
以上より,$\bm{y}_1,\bm{y}_2,\dots ,\bm{y}_n$は1次従属である.
$m=l$のとき,$\bm{y}_1,\bm{y}_2,\dots ,\bm{y}_n$が1次従属であると仮定する.
$m=l+1$のとき,$\{ \bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_{l+1}\}$は$V$の基底であるから,ある
\[ k^{(1)}_1,k^{(1)}_2,\dots ,k^{(1)}_{l+1},\\ k^{(2)}_1,k^{(2)}_2,\dots ,k^{(2)}_{l+1},\\ \vdots \\ k^{(l+2)}_1,k^{(l+2)}_2,\dots ,k^{(l+2)}_{l+1}\in K\]
が存在して
\[ \bm{y}_1=k^{(1)}_1\bm{x}_1+k^{(1)}_2\bm{x}_2+\dots +k^{(1)}_{l+1}\bm{x}_{l+1},\\ \bm{y}_2=k^{(2)}_1\bm{x}_1+k^{(2)}_2\bm{x}_2+\dots +k^{(2)}_{l+1}\bm{x}_{l+1},\\ \vdots \\ \bm{y}_{l+2}=k^{(l+2)}_1\bm{x}_1+k^{(l+2)}_2\bm{x}_2+\dots +k^{(l+2)}_{l+1}\bm{x}_{l+1}\]
となる.
$k^{(1)}_{l+1}=k^{(2)}_{l+1}=\dots =k^{(l+2)}_{l+1}=0$のとき
\[ \bm{y}_1=k^{(1)}_1\bm{x}_1+k^{(1)}_2\bm{x}_2+\dots +k^{(1)}_{l}\bm{x}_{l},\\ \bm{y}_2=k^{(2)}_1\bm{x}_1+k^{(2)}_2\bm{x}_2+\dots +k^{(2)}_{l}\bm{x}_{l},\\ \vdots \\ \bm{y}_{l+2}=k^{(l+2)}_1\bm{x}_1+k^{(l+2)}_2\bm{x}_2+\dots +k^{(l+2)}_{l}\bm{x}_{l}\]
となり
\[ \bm{y}_1,\bm{y}_2,\dots ,\bm{y}_{l+2}\in \langle \bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_l\rangle _{K}\]
であるから,帰納法の仮定より,$\bm{y}_1,\bm{y}_2,\dots ,\bm{y}_{l+2}$は1次従属である.
$k^{(1)}_{l+1}k^{(2)}_{l+1}\dots k^{(l+2)}_{l+1}\neq 0$のとき,ある$i\in \{ 1,2,\dots ,l+2\}$が存在して,$k^{(i)}_{l+1}\neq 0$となる.
このとき,任意の$j\in \{ 1,2,\dots ,l+2\}$に対して
\[ \begin{aligned}\bm{y}^{\prime}_j&=\bm{y}_j-\frac{k^{(j)}_{l+1}}{k^{(i)}_{l+1}}\bm{y}_i\\ &=k^{(j)}_1\bm{x}_1+k^{(j)}_2\bm{x}_2+\dots +k^{(j)}_{l+1}\bm{x}_{l+1}\\ &\quad -\frac{k^{(j)}_{l+1}}{k^{(i)}_{l+1}}(k^{(i)}_1\bm{x}_1+k^{(i)}_2\bm{x}_2+\dots +k^{(i)}_{l+1}\bm{x}_{l+1})\\ &=\left( k^{(j)}_1-\frac{k^{(i)}_1k^{(j)}_{l+1}}{k^{(i)}_{l+1}}\right) \bm{x}_1+\left( k^{(j)}_2-\frac{k^{(i)}_2k^{(j)}_{l+1}}{k^{(i)}_{l+1}}\right) \bm{x}_2\\ &\quad +\dots +\left( k^{(j)}_l-\frac{k^{(i)}_lk^{(j)}_{l+1}}{k^{(i)}_{l+1}}\right) \bm{x}_l\end{aligned}\]
であるから
\[ \bm{y}^{\prime}_1,\bm{y}^{\prime}_2,\dots ,\bm{y}^{\prime}_{l+1}\in \langle \bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_l\rangle _{K}\]
よって,帰納法の仮定より,$\bm{y}^{\prime}_1,\bm{y}^{\prime}_2,\dots ,\bm{y}^{\prime}_{l+2}$は1次従属である.
したがって,ある$(c_1,c_2,\dots ,c_{l+2})\in K^{l+2}\setminus \{ (0,0,\dots ,0)\}$が存在して
\[ c_1\bm{y}^{\prime}_1+c_2\bm{y}^{\prime}_2+\dots +c_{l+2}\bm{y}^{\prime}_{l+2}=\bm{0}\]
となる.このとき
\[ \frac{c_1k^{(1)}_{l+1}+c_2k^{(2)}_{l+1}+\dots +c_{i-1}k^{(i-1)}_{l+1}+c_{i+1}k^{(i+1)}_{l+1}+\dots +c_{l+2}k^{(l+2)}_{l+1}}{k^{(i)}_{l+1}}\neq 0\]
であることに注意すると
\[ \begin{aligned}&c_1\bm{y}_1+c_2\bm{y}_2+\dots +c_{i-1}\bm{y}_{i-1}\\ &-\frac{c_1k^{(1)}_{l+1}+c_2k^{(2)}_{l+1}+\dots +c_{i-1}k^{(i-1)}_{l+1}+c_{i+1}k^{(i+1)}_{l+1}+\dots +c_{l+2}k^{(l+2)}_{l+1}}{k^{(i)}_{l+1}}\bm{y}_i\\ &+c_{i+1}\bm{y}_{i+1}+\dots +c_{l+2}\bm{y}_{l+2}=\bm{0}\end{aligned}\]
となるから,$\bm{y}_1,\bm{y}_2,\dots ,\bm{y}_{l+2}$は1次従属である.
以上より,$\bm{y}_1,\bm{y}_2,\dots ,\bm{y}_n$は1次従属である.
よって,$\bm{y}_1,\bm{y}_2,\dots ,\bm{y}_n$が1次独立ならば,$m\geq n$である.
$\{ \bm{y}_1,\bm{y}_2,\dots ,\bm{y}_n\}$が$V$の基底であるとき,$m>n$であると仮定すると,$\bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_n$は1次従属となり矛盾する.
したがって,$m=n$である.これは,$V$の基底を構成するベクトルの個数が,基底の取り方に依らないことに他ならない.$\blacksquare$
定理1により,次の概念を定義することができる.
$V$をベクトル空間とする.
- $V$の基底を構成するベクトルの個数を$V$の次元(dimension)といい,$\dim V$で表す.ただし,零空間の次元は$0$とし,$V$が定義3の基底を持つときは$\dim V=\infty$とする.
- $\dim V\in \mathbb{N}\cup \{ 0\}$であるとき,$V$を有限次元ベクトル空間(finite-dimensional vector space)という.
- $V$が有限次元ベクトル空間でないとき,$V$を無限次元ベクトル空間(infinite dimensional vector space)という.
具体例で確認しよう.
$n\in \mathbb{N}$とする.
$\mathbb{R}^n$の基底である標準基底は,$n$個のベクトルで構成される.よって,$\dim \mathbb{R}^n=n$である.
連立1次方程式
\[ \begin{pmatrix}1&2&3\\ 3&2&1\\ 2&4&6\end{pmatrix}\bm{x}=\bm{0}\]
の解空間$W$の次元を求める.
$\bm{x}=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$とおくと
\[ \begin{dcases}x_1+2x_2+3x_3=0\\ 3x_1+2x_2+x_3=0\\ 2x_1+4x_2+6x_3=0\end{dcases}\]
これを解くと
\[ \bm{x}=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c\\ -2c\\ c\end{pmatrix}=c\begin{pmatrix}1\\ -2\\ 1\end{pmatrix}\quad (c\in \mathbb{R})\]
よって
\[ W=\left\{ c\begin{pmatrix}1\\ -2\\ 1\end{pmatrix}\ \middle| \ c\in \mathbb{R}\right\} \]
このとき,$\begin{pmatrix}1\\ -2\\ 1\end{pmatrix}$は$W$の基底であるから
\[ \dim W=1\]
基底の必要十分条件
ベクトル空間の基底を構成することによって,その次元を求めることができるが,逆にベクトル空間の次元が分かっているとき,互いに1次独立なベクトルを,その次元の数だけ求めると,そのベクトルの組は基底となる.
$n\in \mathbb{N}$,$K$を体,$V$を$K$上の$n$次元ベクトル空間,$\bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_n\in V$とする.
次の3つの命題は互いに同値である.
- $\{ \bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_n\}$は$V$の基底である.
- $\bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_n$は1次独立である.
- $V=\langle \bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_n\rangle _{K}$
①$\implies$②は定義2より明らか.
②$\implies$③を示す.
\[ \langle \bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_n\rangle _{K}\subset V\]
は明らかに成り立つから
\[ V\subset \langle \bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_n\rangle _{K}\]
を示せばよい.
$\{ \bm{y}_1,\bm{y}_2,\dots ,\bm{y}_n\}$を$V$の基底とする.
このとき,ある
\[ k^{(1)}_1,k^{(1)}_2,\dots ,k^{(1)}_n,\\ k^{(2)}_1,k^{(2)}_2,\dots ,k^{(2)}_n,\\ \vdots \\ k^{(n)}_1,k^{(n)}_2,\dots ,k^{(n)}_n\in K\]
が存在して
\[ \bm{x}_1=k^{(1)}_1\bm{y}_1+k^{(1)}_2\bm{y}_2+\dots +k^{(1)}_n\bm{y}_n,\\ \bm{x}_2=k^{(2)}_1\bm{y}_1+k^{(2)}_2\bm{y}_2+\dots +k^{(2)}_n\bm{y}_n,\\ \vdots \\ \bm{x}_n=k^{(n)}_1\bm{y}_1+k^{(n)}_2\bm{y}_2+\dots +k^{(n)}_n\bm{y}_n\]
すなわち
\[ \begin{pmatrix}\bm{x}_1&\bm{x}_2&\cdots &\bm{x}_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\bm{y}_1&\bm{y}_2&\dots &\bm{y}_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}k^{(1)}_1&k^{(2)}_1&\cdots &k^{(n)}_1\\ k^{(1)}_2&k^{(2)}_2&\cdots &k^{(n)}_2\\ \vdots &\vdots &\ddots &\vdots \\ k^{(1)}_n&k^{(2)}_n&\cdots &k^{(n)}_n\end{pmatrix}\]
となる.
$\bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_n$と$\bm{y}_1,\bm{y}_2,\dots ,\bm{y}_n$は1次独立であるから4
\[ \begin{vmatrix}\bm{x}_1&\bm{x}_2&\cdots &\bm{x}_n\end{vmatrix}\neq 0\]
\[ \begin{vmatrix}\bm{y}_1&\bm{y}_2&\dots &\bm{y}_n\end{vmatrix}\neq 0\]
よって
\[ \begin{vmatrix}k^{(1)}_1&k^{(2)}_1&\cdots &k^{(n)}_1\\ k^{(1)}_2&k^{(2)}_2&\cdots &k^{(n)}_2\\ \vdots &\vdots &\ddots &\vdots \\ k^{(1)}_n&k^{(2)}_n&\cdots &k^{(n)}_n\end{vmatrix}\neq 0\]
であるから,逆行列
\[ \begin{pmatrix}l^{(1)}_1&l^{(2)}_1&\cdots &l^{(n)}_1\\ l^{(1)}_2&l^{(2)}_2&\cdots &l^{(n)}_2\\ \vdots &\vdots &\ddots &\vdots \\ l^{(1)}_n&l^{(2)}_n&\cdots &l^{(n)}_n\end{pmatrix}\coloneqq \begin{pmatrix}k^{(1)}_1&k^{(2)}_1&\cdots &k^{(n)}_1\\ k^{(1)}_2&k^{(2)}_2&\cdots &k^{(n)}_2\\ \vdots &\vdots &\ddots &\vdots \\ k^{(1)}_n&k^{(2)}_n&\cdots &k^{(n)}_n\end{pmatrix}^{-1}\]
が存在する.ゆえに
\[ \begin{pmatrix}\bm{y}_1&\bm{y}_2&\dots &\bm{y}_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\bm{x}_1&\bm{x}_2&\cdots &\bm{x}_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}l^{(1)}_1&l^{(2)}_1&\cdots &l^{(n)}_1\\ l^{(1)}_2&l^{(2)}_2&\cdots &l^{(n)}_2\\ \vdots &\vdots &\ddots &\vdots \\ l^{(1)}_n&l^{(2)}_n&\cdots &l^{(n)}_n\end{pmatrix}\]
であるから
\[ \bm{y}_1=l^{(1)}_1\bm{x}_1+l^{(1)}_2\bm{x}_2+\dots +l^{(1)}_n\bm{x}_n,\\ \bm{y}_2=l^{(2)}_1\bm{x}_1+l^{(2)}_2\bm{x}_2+\dots +l^{(2)}_n\bm{x}_n,\\ \vdots \\ \bm{y}_n=l^{(n)}_1\bm{x}_1+l^{(n)}_2\bm{x}_2+\dots +l^{(n)}_n\bm{x}_n\]
となる.
このとき,任意の$\bm{v}\in V$に対して,ある$k_1,k_2,\dots ,k_n\in K$が存在して
\[ \begin{aligned}\bm{v}&=k_1\bm{y}_1+k_2\bm{y}_2+\dots +k_n\bm{y}_n\\ &=k_1(l^{(1)}_1\bm{x}_1+l^{(1)}_2\bm{x}_2+\dots +l^{(1)}_n\bm{x}_n)\\ &\quad +k_2(l^{(2)}_1\bm{x}_1+l^{(2)}_2\bm{x}_2+\dots +l^{(2)}_n\bm{x}_n)\\ &\quad +\cdots \\ &\quad +k_n(l^{(n)}_1\bm{x}_1+l^{(n)}_2\bm{x}_2+\dots +l^{(n)}_n\bm{x}_n)\\ &=(k_1l^{(1)}_1+k_2l^{(2)}_1+\dots +k_nl^{(n)}_1)\bm{x}_1\\ &\quad +(k_1l^{(1)}_2+k_2l^{(2)}_2+\dots +k_nl^{(n)}_2)\bm{x}_2\\ &\quad +\cdots \\ &\quad +(k_1l^{(1)}_n+k_2l^{(2)}_n+\dots +k_nl^{(n)}_n)\bm{x}_n\end{aligned}\]
となるから
\[ \bm{v}\in \langle \bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_n\rangle _{K}\]
すなわち
\[ V\subset \langle \bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_n\rangle _{K}\]
を得る.
③$\implies$①を示す.
$\bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_n$が1次独立であること(②)を示せばよい.
$\bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_n$が1次従属であると仮定すると,ある$k_1,k_2,\dots ,k_n\in K^n\setminus \{ (0,0,\dots ,0)\}$が存在して
\[ k_1\bm{x}_1+k_2\bm{x}_2+\dots +k_n\bm{x}_n=\bm{0}\]
となる.このとき,ある$i\in \{ 1,2,\dots ,n\}$が存在して,$k_i\neq 0$となるから
\[ \bm{x}_i=-\frac{k_1}{k_i}\bm{x}_1-\frac{k_2}{k_i}\bm{x}_2-\dots -\frac{k_n}{k_i}\bm{x}_n\]
である.
任意の$\bm{v}\in V$に対して,ある$l_1,l_2,\dots ,l_n\in K$が存在して
\[ \begin{aligned}\bm{v}&=l_1\bm{x}_1+l_2\bm{x}_2+\dots \\ &\quad +l_{i-1}\bm{x}_{i-1}+l_i\bm{x}_i+l_{i+1}\bm{x}_{i+1}\\ &\quad +\dots +l_n\bm{x}_n\\ &=l_1\bm{x}_1+l_2\bm{x}_2+\dots +l_{i-1}\bm{x}_{i-1}\\ &\quad -l_i\left( \frac{k_1}{k_i}\bm{x}_1+\frac{k_2}{k_i}\bm{x}_2+\dots +\frac{k_n}{k_i}\bm{x}_n\right) \\ &\quad +l_{i+1}\bm{x}_{i+1}+\dots +l_n\bm{x}_n\\ &=\left( l_1-\frac{k_1l_i}{k_i}\right) \bm{x}_1+\left( l_2-\frac{k_2l_i}{k_i}\right) \bm{x}_2\\ &\quad +\dots +\left( l_{i-1}-\frac{k_{i-1}l_i}{k_i}\right) \bm{x}_{i-1}\\ &\quad +\left( l_{i+1}-\frac{k_{i+1}l_i}{k_i}\right) \bm{x}_{i+1}\\ &\quad +\dots +\left( l_n-\frac{k_nl_i}{k_i}\right) \bm{x}_n\end{aligned}\]
となるから
\[ \bm{v}\in \langle \bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_{i-1},\bm{x}_{i+1},\dots ,\bm{x}_n\rangle _{K}\]
よって
\[ V=\langle \bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_{i-1},\bm{x}_{i+1},\dots ,\bm{x}_n\rangle _{K}\]
であり,$\bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_{i-1},\bm{x}_{i+1},\dots ,\bm{x}_n$は①次独立であるから,$n-1$個のベクトルの組$\{ \bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_{i-1},\bm{x}_{i+1},\dots ,\bm{x}_n\}$は$V$の基底である.
これは$\dim V=n$であることに矛盾する.
したがって,$\bm{x}_1,\bm{x}_2,\dots ,\bm{x}_n$は1次独立である.$\blacksquare$
- これについては,次の記事を参照するとよい.
https://mathabyss.com/wait ↩︎ - 次の記事の命題1を参照するとよい.
https://mathabyss.com/linear_independent-dependent ↩︎ - 次の記事の定理1を参照するとよい.
https://mathabyss.com/linear_independent-dependent ↩︎ - 次の記事の定理1を参照するとよい.
https://mathabyss.com/linear_independent-dependent ↩︎